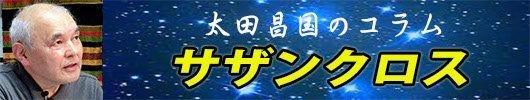・レイバーフェスタ2025
・レイバーネットTV(12/10)
・あるくラジオ(11/1)
・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告
・ブッククラブ(12/13)
・シネクラブ(10/11)
・ねりまの会(6/28)
・フィールドワーク(6.1報告)
・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)
・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画
●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10)
●〔週刊 本の発見〕第416回(2025/12/25)
●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6)
●川柳「笑い茸」NO.164(2025/11/25)
●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)
●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14)
●「美術館めぐり」第18回(2025/12/22)
★カンパのお願い
■メディア系サイト
原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP
|
|
|
ログイン |
|
情報提供 |
|
|
|
Status: published View |
●第103回 2025年7月15日(毎月10日)
ネット全盛の時代に、或る日の新聞国際欄を読み尽くす
 「レイバーネット日本」ニュースレター95号(2025年7月1日/写真)に掲載された松原明「歩き続けるレイバーネット 第7回『一億総ユーチューバー時代』」は興味深い逸話を紹介している。松原は、最近の「若者は新聞もとらずテレビも見ないと言われている」ことは知っていたが、若者と接する機会が多い一大学教師から次の生情報を聞いて驚いたというのだ。「若者のテレビ離れが言われているが、最近130人の学生からアンケートを取ったところ、NHKを見ている人はゼロだった」。「下宿生でテレビを持っている人はゼロ、実家にいる人はテレビはあるがほとんど見ていない。テレビ由来のニュースやドラマは、ネットを通じて見ているケースがほとんど」――この話を聞いた松原は言う。「こうした『読まない、考えない、見るだけ』の若者の登場は、社会全体の民主主義の後退と軌を一にしていると思う」。
「レイバーネット日本」ニュースレター95号(2025年7月1日/写真)に掲載された松原明「歩き続けるレイバーネット 第7回『一億総ユーチューバー時代』」は興味深い逸話を紹介している。松原は、最近の「若者は新聞もとらずテレビも見ないと言われている」ことは知っていたが、若者と接する機会が多い一大学教師から次の生情報を聞いて驚いたというのだ。「若者のテレビ離れが言われているが、最近130人の学生からアンケートを取ったところ、NHKを見ている人はゼロだった」。「下宿生でテレビを持っている人はゼロ、実家にいる人はテレビはあるがほとんど見ていない。テレビ由来のニュースやドラマは、ネットを通じて見ているケースがほとんど」――この話を聞いた松原は言う。「こうした『読まない、考えない、見るだけ』の若者の登場は、社会全体の民主主義の後退と軌を一にしていると思う」。
このニュースを読み終えた直後、私は購読している「しんぶん赤旗」の7月13日号を開いた。紙面を埋め尽くす選挙や党勢拡大に関する記事はほとんど読まないが、同紙の国際欄と文化欄には、他紙では読めない記事がときどき載る。だから、読んでいないと落ち着かない。特に国際欄には、欧州駐在の特派員によっては、民族・植民地問題に関わる重要な動きを丹念に、系統的に追う記事が載る場合があるから、重要だ。
この日の国際欄に特別な大見出しの記事があったわけではない。控え目な見出しの記事が6〜7点ほど載っている。真ん中に「中国抗日戦争記念館 新展示が始まる」という見出しの囲み記事がある。「うらみでなく平和のために」との副見出しもある。北京駐在の特派員の記事だ。同記念館があるのは北京市郊外、日本が中国侵略を本格化した盧溝橋事件(1937年7月7日)の現場近くに、1987年に建てたものだという。しばらく休館して、展示面積が2倍になった。目を引くのは、日本軍が中国に対して行った侵略行為の数々――南京大虐殺、上海や重慶への無差別爆撃、女性への性暴力、731部隊による細菌戦などの展示だという。館長は「展示の目的は日本に対するうらみを宣伝するものではない。歴史の中から教訓を引き出し、日中人民や世界の人びとが平和を大切に思い、未来に向かうためだ」を語る。館長の最後の言葉があることで、記事に膨らみが生まれている。
その下には「カンボジア大虐殺現場が世界遺産に」と題する【パリ=時事】の記事がある。1970年代クメール・ルージュ政権下で行なわれた大虐殺の現場(=キリング・フィールド=殺戮の原野)であるチュンスク虐殺センター(処刑場場跡)や首都プノンペンのトゥールスレン虐殺博物館(旧収容所跡)を、ユネスコが世界遺産に指定したとのニュースだ。私は、以前にも書いたが、同政権下で国家幹部会議長を務めたキュー・サムファン(1931〜)がパリ留学時代の若き日に書いた博士論文「カンボジア経済と工業化の問題」(1959年執筆。D・ボゲット/鵜戸口哲尚=編『カンボジアの悲劇』所収、成甲書房、1979年)には、第3世界の視点からする新帝国主義論の一つとして大きな関心をもってきた。のちに同政権幹部に就任することになる人びとの多くは、キュー・サムファンと同じ時代にパリに留学していた。時代は、ベトナムにおけるフランス植民地主義の敗北と撤退(ディエン・ビエン・フーの戦い。1954年)の直後であり、アルジェリアにおける独立運動の高揚、フランスの若者たちの徴兵拒否運動(ボリス・ヴィアンが作詞し、日本では沢田研二がカバーしている「脱走兵」という曲は、この時代を背景に作られ、歌われ始めた抵抗歌だ)、アルジェリア現地におけるフランス植民地軍の残虐行為の頻発などがフランス社会全体を揺るがせていた。それを目の当たりにしたカンボジアからの若い留学生たちは、そこから階級差なき未来社会を夢み、帰国後に祖国解放闘争に投企したはずだった。その彼らがいざ国家権力を掌握した時代に、あの惨劇をもたらしたことは、私にとって大きな衝撃だった。カンボジアでは、まだしも、1975年から79年にかけて政権の座にいたクメール・ルージュの指導者たちを裁く特別法廷が開かれたが、キュー・サムファンは最後まで、虐殺に関して「知らぬ存ぜぬ」の態度を貫き通した。若いころの、さわやかな彼の顔つきからも、上記論文の構成論理からも、想像もつかない晩年の姿ではあった。
これら一連の出来事は、日本および他国・他地域における社会変革運動の在り方、その挫折、権力掌握後の重大なる失敗、革命の過程で大きな役割を果たした軍隊(ゲリラ、解放軍、遊撃隊、人民軍etc.)を革命後の社会でも重用すること、すなわち軍事力偏重の社会となることの危険性……などを再検討するよう、私に迫った。人間社会の在り方に関して理想主義を掲げることで倫理の高みに立ちうる社会変革の理念は、実践において、ヨリ厳しい批判的検証の対象とされるのは当然のことだ。カンボジア虐殺現場の世界遺産指定のニュースは、その思いをいっそう深めてくれた。これら2つの記事は「赤旗」ならではの記事だ。
国際欄を埋める残りの記事の紹介を急ぐ。【ベルリン=時事】の記事は、旧ユーゴスラビア構成国のボスニア・ヘルツェゴビナでは、紛争下の1995年に東部スレブレニツァでセルビア人勢力がイスラム教徒のボシュニャク人8300人以上を殺したジェノサイドから30年の追悼行事が行われたと報じている。
ロイター電の報道によれば、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)は、パレスチナ・ガザ地区での「ガザ人道財団(GHF)」の食糧配給所で、6週間で少なくとも798人が殺害されたと発表した。GHFは、国連主導の人道支援の枠組みを避け、米国の民間警備会社や運送業者を使い、イスラエル軍の管理地域で食料配布を行なっているが、OHCHRは「さらなる残虐行為が行われる危険」を警告している。
イタリア出身の国際弁護士で、イスラエルによるガザ地区でのジェノサイドを告発してきた国連特別報告者のフランチェスカ・アルバネーゼは、イタリアTVでのインタビューで、トランプ米政権が彼女に制裁を科すと発表したことに触れて、「マフィアを想起させる手法だ」「これは強さの表れではなく、帝国がいかに弱く、衰退しているかを示すものだ」と語った。さらに曰く、「私は背筋を伸ばして仕事を続ける。ガザでのジェノサイドの終結を求める無数の人々と共に頭を上げて仕事をしている」。
最後に来る記事も、これと関連する。【ワシントン】駐在記者の記事だ。国連本部で開かれた国連刑事裁判所(ICC)の締約国会議で発言した米政府代表は、ICCに対してイスラエルのネタニヤフ首相らの逮捕状を取り下げ、「米国と同盟国イスラエルに対する捜査をやめることを期待する」と述べた。米国とイスラエルはICCには未加盟だが、オブザーバーとして出席し、ここまでの発言を行なったものらしい。
これらの記事が、同じ日の国際欄一面にひしめき合っている。読み進めていくと、2025年現在の世界の状況が如実に浮かび上がってくるような記事の配置である。そこには歴史的過去に触れた記事も、現在進行中の事態を伝える記事もあるが、総体として、人類が刻んできている愚かな行為、つまりは愚行を思い起させる記事群には違いない。だが、これが、人類の過去・現在・未来をふりかえるための出発点なのだ。
ここからでも何らかの希望を見出すのか、それとも絶望に浸るのか。それは、個々人の生き方の問題に関わってこよう。
若者は若者で、ネット空間を唯一神とする情報管理の罠に気づいて、今後これを突破する方法を編み出すかもしれない。新聞を読み慣れ、一つの紙面に掲載されている異種の記事の相互関連を探ったり、そこから或る時代の特徴を掴み取ることが習慣化しているわれわれの世代も、ネット空間からも刺激を受けながら試行錯誤を続けている。私は、今秋から5か月間、週に一度、若い学生と触れ合う機会が待ち受けているので、大いなる試練にさらされるのだと緊張している。(文中敬称略)
Created by staff01. Last modified on 2025-07-15 12:59:50 Copyright: Default