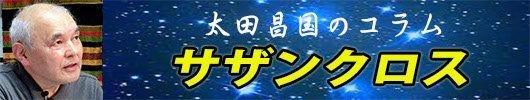●第104回 2025年8月15日(毎月10日)
まだ見ぬ、731部隊をめぐる中国映画をめぐって
 「PTSD(心的外傷後ストレス障害)の日本兵家族会・寄り添う市民の会」(黒井秋夫代表/写真)が活動を始めたのは2018年のことだった。アジア太平洋戦争に日本軍兵士として出兵した男親の暴力、酒浸りの日々、そして無気力な言動に辟易とさせられながら子ども期・思春期・成人期を送り、「軽蔑すべき」その親が死んで「ほっと」してしばらく経ってから、偶然にもテレビ番組か映画か書物を通して、米国で戦争体験の後遺症に苦しむ元軍人の存在を知り、自分の親はこれだったのではないか、と思い至った人びとの活動である。軍歴と所属部隊を知り、その部隊はアジア太平洋のどこで、どんな戦争を担ったのか、どんな加害行為を行なったのかを調べる。「出征」前の父親のひととなりを母親から聞いて、皇軍兵士になる「前」と、敗北した皇軍兵士の「後」を隔てる万里の壁に絶句する。加害行為に加担したことで、自分の親は退役したのちに精神的に崩壊し、もはや日常生活に復帰できなかったのではないか、と推定する。その体験を人前で証言する――さまざまな活動が積み重ねられてきた。私は証言集会へ行く機会はこれまでもてなかったが、これを取り上げた新聞記事、テレビ番組、書物にはできる限り触れてきた。
「PTSD(心的外傷後ストレス障害)の日本兵家族会・寄り添う市民の会」(黒井秋夫代表/写真)が活動を始めたのは2018年のことだった。アジア太平洋戦争に日本軍兵士として出兵した男親の暴力、酒浸りの日々、そして無気力な言動に辟易とさせられながら子ども期・思春期・成人期を送り、「軽蔑すべき」その親が死んで「ほっと」してしばらく経ってから、偶然にもテレビ番組か映画か書物を通して、米国で戦争体験の後遺症に苦しむ元軍人の存在を知り、自分の親はこれだったのではないか、と思い至った人びとの活動である。軍歴と所属部隊を知り、その部隊はアジア太平洋のどこで、どんな戦争を担ったのか、どんな加害行為を行なったのかを調べる。「出征」前の父親のひととなりを母親から聞いて、皇軍兵士になる「前」と、敗北した皇軍兵士の「後」を隔てる万里の壁に絶句する。加害行為に加担したことで、自分の親は退役したのちに精神的に崩壊し、もはや日常生活に復帰できなかったのではないか、と推定する。その体験を人前で証言する――さまざまな活動が積み重ねられてきた。私は証言集会へ行く機会はこれまでもてなかったが、これを取り上げた新聞記事、テレビ番組、書物にはできる限り触れてきた。
子ども時代から、私の周りには戦死者も出兵者もいなかったので、私個人としては必ずしも切迫した問題ではなかった。そのこと自体も問題だと今でこそ思うが、事実はそうでしかなかった。だが、米国のベトナム侵略戦争が米軍の敗北・撤兵によって終わりを告げた1975年以降、米国から届くニュースには、ベトナム帰還兵の犯罪(家庭内暴力、無差別の銃乱射による大量殺人、精神的な錯乱行為、麻薬漬けetc.)に触れたものが多くなった。それは、湾岸戦争、アフガニスタンとイラクを主戦場とした「対テロ戦争」後にも続く。1960年に海兵隊員として沖縄に駐留した経験を持つ政治学者、ダグラス・ラミスは、本土が戦場になった経験を持たないにもかかわらず海外を戦場とする戦争を常に続けている米国に「戦争が帰ってくる」と表現したことがある。PTSDに苦しむ元兵士たちが帰国後に引き起こす暴力事犯を指して、こう言ったのだ。これを的確な視点だと考えた私は、この事実を「反戦争論」の重要な論拠のひとつとしてきた。
それからしばらくして、精神病理学者の野田正彰が『戦争と罪責』という本を出版した(岩波書店、1998年。現在は岩波現代文庫所収)。冒頭の一節に、野田の問題意識が明確に出ている。「戦争の加害者も被害者もひっくるめて無罰化し、勝っても敗けても戦争は悲惨なものだ」とする「無罰化」意識に支えられて、戦後日本の反戦・平和運動は展開されてきた。「(日本の)自分たちが何を行い、何を失ったのか、直視しようとしない」思考態度がそこでは貫かれてきた。そこで著者は、戦地で残虐な行為を行った将校、軍医、憲兵などの旧兵士たちに対して丹念な聞き取り調査を行い、彼らがそれに関して感じてきた罪の意識を問い、それをなした自分とどう向き合ってきたかを解明しようとしたのだった。米国だけではない、やはり、酷い戦争をしてしまった国ではどこでも、戦時中の自分が犯した残虐な行為を誰にも話すこともできず、心中に闇を抱え込んだまま生きてきた人びとがいたのだ。「大日本帝国皇軍には、心を壊す兵士など存在するわけはない」という、支配層が発してきたであろう建前的なメッセージに固く縛れて、日本の旧皇軍兵士たちは、米国の元兵士たちのように社会的に「暴発」するのではなく、ごく身近な妻と子だけに向けて暴力を行使したり、無気力の裡に沈潜したりしていたのだろうか。家族も、そんな夫(あるいは父)の存在を恥じて、決して外に向かって語らなかったのだろうか。
野田の著書が現れて四半世紀――子どもたちは、いま、旧皇軍兵士であった父親のことを語り始めている。当事者にもっとも身近な場所にいた人びとの証言だから、近親者であるがゆえの憎愛がこもる。だからこそ、言葉には真実さが溢れていると思える。そこで語られるどの言葉にも、「(戦後)情けない生き方をした」父の背後には、皇軍兵士だった父たちによって殺害・虐待されたアジアの人びとの姿を感じ取る姿勢が溢れている。
思い起こせば、私が中学3年生だった時には、例えば、神吉晴夫編『三光――日本人の中国における戦争犯罪の告白』という本は出ていた(光文社、カッパブックス、1958年)。「殺光、焼光、略光、これを三光という。殺しつくし、焼きつくし、奪いつくすことなり」という恐ろしい言葉がカバーには書かれていた。日本の敗戦直後には旧ソ連のシベリア・ハバロフスクの捕虜収容所に、そして1949年の中華人民共和国成立後しばらくしてからは中国・撫順の戦犯管理所に収容される日々を送るうちに、皇軍が行なったアジア侵略戦争に加担した自分に「臍を噛むような痛恨にさいなまれながら」書かれた元兵士の手記である。彼らはその後も「中国帰還者連絡会」「撫順の奇跡を受け継ぐ会」などの活動を通じて、戦争への内省を深め、日中友好のために尽力した。
戦争トラウマを内向させた旧皇軍兵士には、その道は開かれていなかった。ひたすら裡に籠もって過去を自己内に封殺し、他人に打ち明けることも、被害者に詫びることもなかった。父親の後半生の生き方を訝しく思った子ども世代の手によって、事の真相が明かされつつある。敗戦から70年〜80年を経ての大事な動きだと思える。
折しも、皇軍の侵略による被害を受けた地域のひとつ=中国からは、「抗日戦争勝利80周年」の記念行事の様子が伝えられてくる。映画『南京写真館』は日本軍の南京虐殺を記録した写真を守り抜いた南京の、或る写真館の姿を描いたもののようだ。『731』は、文字通り、旧日本陸軍が中国東北部のハルビンに創設して、細菌兵器の研究と中国各地での使用・中国人捕虜らへの人体実験などを行った秘密機関「731部隊」をめぐる映画のようだ。映画の評価は見てからしか行うことはできないが、これらの映画の公開予定を報じる日本のメディアは、いずれも「中国国民の対日感情が悪化する可能性がある」という言葉遣いを行なっている。8月2日付け『しんぶん赤旗』ですらが、『北京に住む30代の男性は「731部隊が映像化されれば、人々の日本をうらむ感情があおられる懸念がある」と語りました。』と北京駐在特派員が報じている。
731部隊に関しては、当事者による重大な証言もあり、隊員3607人分の名簿も(遅きに失して2018年になってからだが)開示され、研究者・作家・ジャーナリストらによる調査・研究書も積み重ねられてきた。だが、政府は、今年2025年3月の国会答弁に至っても「資料がない」とシラを切る。共産党の山添議員が、防衛省防衛研究所戦史研究センター資料室に保存されている公文書にある、生きた捕虜に毒ガス弾を大量に射撃したとか、毒ガス水溶液を捕虜に飲ませたとかの「臨床的症状の観察記録」を提示して質問しても、石破首相は「(事実を検証する)手立てが歴史とともに失われた」と答えた(『しんぶん赤旗』25年3月22日付け、『朝日新聞』25年8月13日付け)。
敗戦から80年後の現政権が、731部隊が実際に行っていた「実験」内容を、資料がないと言って、事実の曖昧化を図る。14歳で満州に誘われ、敗戦までの半年間だけ731部隊に所属したひとがいる。帰国後は沈黙を貫いてきたが、2015年「731部隊の展示企画展」に出会って、意を決した。ハルビンの部隊本部棟で観た光景(「標本室」のガラス瓶には、捕虜を解剖して、ホルマリン漬けにした内臓、手足、頭部が浮かんでいた)を語り、ハルビン郊外の中国人慰霊碑の前で手を合わせて、謝罪する。すると、日本のSNSは「ボケ老人」「迷惑高齢者」との誹謗中傷の投稿で大荒れとなる(同上「朝日新聞」)。
中国で作られる731部隊や南京虐殺をテーマにした映画が「対日感情を悪化させる恐れがある」との、本末転倒の懸念(危惧)報道がなされるのは、日本社会のこんな水準を思えば、「当然のこと」なのだろう。しかし、この「当然のこと」は、もちろん、批判にさらし、転倒されなければならない。
映画自体に即しての批評は、実際にこの映画を見ることができれば、改めて行いたい。
Created by staff01. Last modified on 2025-08-15 16:41:21 Copyright: Default