
「生きろ」という強烈なメッセージ
『宝島』(真藤順丈、講談社)/評者:渡辺照子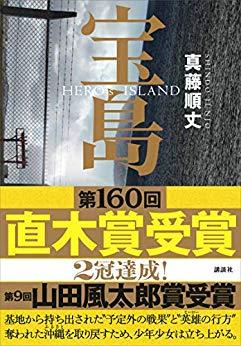
ストーリー展開の巧みさは無論のこと、描写力が素晴らしい。沖縄の海底を「無数の絵の具を溶かしたような色の氾濫」と書き、米兵の英語を「細くとがらせたような異国の言葉」とし、刑務所での強制労働のきつさを「体じゅうの筋肉が骨からはがれ落ちそうになってくる」と伝える。この小説を読み、まず思ったのはインパクトある映画になるなということ。格闘シーンはスピード感があり、人物が受けた傷の痛みや心臓の高鳴りまで我がことのように思えるのだからむしろ映像を超えたかもしれない。文章は身体性を持ち、読む者の五感に訴え、乏しい想像力を喚起する。
基地に占拠されてしまった先祖代々の土地で暮らす沖縄の人たちが受ける過酷さは何度でも語られる。その中で生き延びてきた人たちのたくましさが、今の辺野古の闘いの強さにつながるのだろう。いつも力ある者に殺されてきた怒りと、生きていることへの賛歌による明るさとの共存が、本土に生まれた私たちの心をとらえて離さない。ゆるぐことのない沖縄への憧憬。作者の思いもそこにある。 私は沖縄の人たちが歴史的に受けている重層的な差別・抑圧構造を見る。米国VS日本政府、本土VS沖縄、米兵VS沖縄の男性、沖縄の男性VS沖縄の女性、とあたかもミルフィーユのようだ。特に、主要人物の一人である若者が、長年慕っていた女性を強制性交する場面は悲しかった。
読む者の胸を突き刺すような言葉を様々な人物に語らせているのも印象深い。「わたしが守らなければならないのは、良心ではなくて治安だ」という米軍関係者の言葉。おばあの「暗い感情に呑みこまれたらならん、恨みや憎しみで目を曇らせたらならんよ」の言葉。「どんなに無謀な青写真でも、現実味のない究極の理想でも、おれたちは本気でつかみにいかなきゃならない」は、特定の人物ではなく作者が設定した語り部の言葉だ。
なぜかくも沖縄の人たちは苛まれるのか、誰が何のためにそれをするのか。読者はそのループに無関係でいられるのか。その問いは最終章で明らかになる。ネタバレになるのを覚悟で書かせてもらおう。沖縄の人たち、女性も子どもも容赦なくいたぶる米軍の元締め。その正体を追い詰める最後の大団円になろうかという個所だ。「これが謎解きの極みだ。エンターテインメント性が高い」と読み進めると大きな裏切りに合う。その張本人(複数いる)が「ダニー岸」という符牒で呼ばれることが明らかになりそうな時の文章といったらない。「アメリカの利益とみずからの存在意義を同化させて、この沖縄の現実を本土から遠ざけることに、対岸の火事のままに保つことに血道を上げるすべての日本人が、“ダニー岸だったのさ」。この拙稿の冒頭で「小説の醍醐味云々」と書いた自分が恥ずかしい。小説というフィクションの世界から、ヌッと太い腕が伸び出て私は胸倉をつかまれたようだった。「自分は安全圏に身を置いて、この小説をひとごとのように楽しむおまえは一体なんなのだ。」と迫られたのだ。
それに符牒としての名称「ダニー岸」が暗示的だ。「ダニー」はよくある男性の英語名。しかし、「岸」はなぜ「岸」なのだろうか。そうだ、安倍晋三の祖父、「岸信介」の「岸」ではないのか。そして、凡庸な「ダニー」は忌み嫌われる「ダニ」のことではないか。私は勝手にかような暗号と受け取る。
「生きろ」という強烈なメッセージ。暴力にさらされ、常に死と隣り合わせの日常が、生きていることを無条件に肯定する。日本には真の抵抗の歴史がないと言う。ならば沖縄はどうだ。沖縄は本土、米国に抵抗しつつ馴れつつ、生き延びてきたのではないか。私は、時に息をつめ、時に呼吸を早め、涙し、唇をかみしめながら読んだ。これはフィクションだが、報道や歴史の教科書では描き切れない沖縄がある。豊穣な「生命のエネルギー」に満ち溢れた小説だ。 「平成」でも「令和」でもない我々の時代に、この小説の最後の言葉を掲げよう。「そろそろほんとうに生きるときがきた」。
*「週刊 本の発見」は毎週木曜日に掲載します。筆者は、大西赤人・渡辺照子・志真秀弘・菊池恵介・佐々木有美・佐藤灯・金塚荒夫ほかです。
Created by staff01. Last modified on 2019-04-10 22:57:05 Copyright: Default
