
・レイバーフェスタ2025
・レイバーネットTV(12/10)
・あるくラジオ(11/1)
・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告
・ブッククラブ(12/13)
・シネクラブ(10/11)
・ねりまの会(6/28)
・フィールドワーク(6.1報告)
・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)
・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画
●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10)
●〔週刊 本の発見〕第416回(2025/12/25)
●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6)
●川柳「笑い茸」NO.164(2025/11/25)
●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)
●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14)
●「美術館めぐり」第18回(2025/12/22)
★カンパのお願い
■メディア系サイト
原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP
|
|
|
ログイン |
|
情報提供 |
|
|
|
Status: published View |

なぜ、パレスチナ人に対するジェノサイドが止まらないのか?
『イスラエル=アメリカの新植民地主義 ガザ〈10.7〉以後の世界』(地平社、ハミッド・ダバシ 著)、早尾貴紀 訳) 評者:志水博子
著者は米国在住のイラン人ハミッド・ダバシ(写真下)。初めて聞く名だ。それどころか、イラン人の書いたものを読むこと自体が初めてだ。「訳者まえがき」に、彼が中東ニュースサイトに連載している記事のうち、2023年10月7日のガザ一斉蜂起の後に発表したものを集成して1冊にしたとある。「ガザ一斉蜂起」!ちなみにNHKのニュースでは、10月7日は「イスラエルにイスラム組織ハマスが大規模攻撃」した日とされている。この違いが本書のテーマといってもいい。さらに、「訳者まえがき」には、「本書の随所でダバシはパレスチナ/イスラエル問題の本質が、欧米の入植者植民地主義(セトラー・コロニアリズム)であるということを繰り返し、そしてイスラエルという国家そのものが入植者植民地(セトラー・コロニー)であると断じている」とある。およそ、日本のマスメディアでは見慣れない表現である。
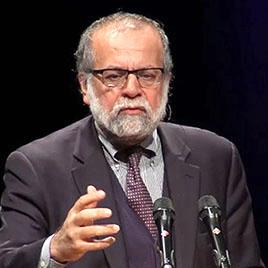
本書を読みながら、正直わからないところは多々あった。日本でごくフツーの生活を送り情報に接している限り、それとはまったく別の視座からの情報だけに咀嚼することさえ難しかった。その時に役立ったのは訳者の【解説】であった。その手助けもあって、私のなかに巣食う西洋的近代への信奉が崩れていくある種の醍醐味のようなものがあった。31章のうち、特に印象的であったいくつかの章を紹介しておこう。
1章「欧米はいかにイスラエルを『再発明』しているか」
米国前大統領バイデンの、「これは我々が行う30億ドル規模の投資の中で最も価値のあるものだ。もしイスラエルのようなものが存在しなかったならば、アメリカ合衆国は中東地域における自国の利益を守るために別のイスラエルでっち上げなければならないだろう。」という言葉から始まる。著者はこう解説する。「この2週間のあいだに、米国は悪辣なイスラエルの軍隊に攻撃手段を与えて強化し、さらに好戦的で暴力的なイスラエルを再びでっち上げた」と。それは「つまりイスラエルを、ホロコーストに至ったヨーロッパの残忍な歴史からのユダヤ人の避難場所としてではなく、機能不全に陥った帝国[米国]の最大の利益を守る軍事基地にした」ということなのだと。また、「シオニズム運動によるイスラエル建国は、ユダヤ教による王国の復活などではなく、むしろユダヤ教に反したユダヤ人国家の『捏造』、つまり近代ヨーロッパの植民地主義と人種主義によってパレスチナを支配・収奪して作られた『入植者植民地国家』だ」と。私たちは欧米のパレスチナに対するあり方を今一度検証する必要がある。その時に本書は道標になる。
3章「『川から海まで』のスローガンを取り戻す」
日本でも著名な『オリエンタリズム』を著したエドワード・サイードの「一国家解決」が紹介されている。訳者をしてダバシはサイードの仕事を継承する思想家と評されるが、この章に限らず、サイードの論考はある種の敬意をもって紹介されている。また、サイードについては、14章「米国大学キャンパスにおける抗議運動―エドワード・サイードは、この瞬間を大切にしたことだろう」において、「アメリカの大学のキャンパスは今日、シオニストの覇権が終焉を迎える場となっている」と記している。生涯を闘争に捧げたサイードに対するオマージュともいえる著者の熱い思いが伝わってくる。
5章「イスラエルの対ガザ戦争にはヨーロッパ植民地主義の歴史全体が含まれている」
タイトル通りである。既成の、すなわち西洋的「世界史」の価値観ではなく、次のように記されている、「イスラエル人がパレスチナでやっていることは、フランス人がアルジェリアで、イギリス人がインドで、ベルギー人がコンゴで、アメリカ人がベトナムで、スペイン人がラテンアメリカで、イタリア人がアフリカで、ドイツ人がナミビアでやったことと同じであり、それはヨーロッパによる大量虐殺の歴史に加えられたもうひとつの章」だと。さらに【解説】では、「入植者植民地主義」について、「日本の北海道も、それだけで独立国家というわけではないが、アイヌのちに日本の和人が集団で入植し、先住民のアイヌを虐殺・排除しながら領土・資源を奪って、日本の一部としての北海道へと変造されたものだ。そういう意味で入植者植民地主義だということができる」と記されている。このように、訳者解説は、西洋的価値観を打ち砕く情報だけではなく、西洋の植民地主義と地続きの日本のそれについても触れている。
6章「ガザのおかげでヨーロッパ哲学の倫理的破綻が露呈した」
ドイツの著名な哲学者の批判から始まり、著者は次のように述べる、「・・ホロコーストの罪悪感からドイツ人はイスラエルに強固に献身するようになった、というのが通説だ。しかしヨーロッパ以外の世界にとっては、南アフリカ共和国が国際司法裁判所に提出した壮大な文書が証明しているように、ドイツがナチス時代に行なったことと、シオニスト時代に現在行なっていることの間には、完全な一貫性がある」と。そして、この章をこう結ぶ、「今日、私たちがこうして解放されたのは、パレスチナ人のような諸民族が世界各地で苦難を被っているおかげである。彼らの長年にわたる歴史的なヒロイズムと犠牲によって、「西欧文明」の基盤にある恥知らずな野蛮さがついに分解され取り出されたのだ」と。それは、9章「ヘーゲルの人種差別的哲学が、ヨーロッパのシオニズムに与えた影響」にもつながる。はて、では、私たちは著者がいうように「解放」されているのだろうか。いまだその途上かもしれない。
その他、10章「米国大統領選―バイデンとトランプは殺人コインの表裏である」、17章「老化したバイデンとリベラル帝国主義の危機」、18章「ドナルド・トランプ暗殺未遂は、アップルパイ並みにアメリカ的だ」、19章「バイデンと同じく、カマラ・ハリスは、イスラエルの大量虐殺に全面賛同している」、24章「米国大統領選挙で、なぜ有権者はファシズムと大量虐殺的シオニズムのどちらかを選ばなければならないのか」、25章「ニューヨーク・タイムズ紙は反ユダヤ主義を封じても、ジェノサイドには触れない」、31章トランプが異常なわけではなく、外国人嫌悪はアップルパイ並みにアメリカ的なのだ」では、相変わらず世界の帝国であり植民地主義国家の親玉としてのアメリカのどうしようもない絶望的な状況が描かれている。
では、本書は絶望で終わるのか、というとそうではない。8章「評論家たちはいかにフランツ・ファノンの遺産を歪曲しているか」、11章「フランチェスカ・アルバネージを恐れるのは誰か?」、20章「コリー・ブッシュが人種差別と植民地主義の勢力に立ち向かった」、21章「ハイファの隠された歴史が静かで美しいパレスチナ映画の中に姿を現す」、23章「タナハシ・コーツは、いかにしてリベラル・シオニズムから脱却したか」、29章「イスラエルとアメリカの蛮行が歴史の負け組にあることを示す4冊の本」、30章「マフサ・アミーニーの抗議はイラン政権と反対派、双方の失敗を露呈した」等には、ポストコロニアリズムの、その先の世界へ導く道が用意されている。訳者があとがきで、「この幾重にも屈折・歪曲させられたシオニスト的世界に、どのように抵抗する可能性を見出しているのだろうか。」「在米パレスチナ人批評家の故エドワード・サイードを受け継ぐダバシが、たんに批判と絶望を語って終わるはずがない。むしろサイード以上に反抗する主体を見出すことに熱心であったダバシは、植民地支配に抵抗してきた歴史の中に参照すべき思想運動を指摘する」とある所以だ。
最後のイスラエル・イラン、そしてアラブ諸国の関係についての論考に触れることができなかったが、それらを読むと、「停戦」の企みも見えてくる。この1冊で中東を理解したとはとても言えないが、少なくとも、今私が暮らす日本と地続きの世界として中東が見えて来たようには思う。
Created by staff01. Last modified on 2025-06-27 16:29:52 Copyright: Default

