
「コロンブスから五百年」いまも続く抵抗
『チリ 嵐にざわめく民衆の木よ』(文・高橋正明、写真・小松健一、大月書店、1990年)評者:根岸恵子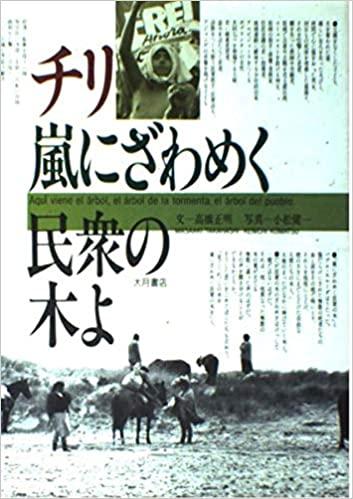
昨年5月にアメリカでジョージ・フロイドさんが警官に殺され、ブラック・ライブス・マターがこれまでになく世界的に拡大して、植民地時代の人種差別にまで遡り人々が声をあげるのを見て、はたと今から30年前の「コロンブスから五百年」の抵抗運動を思い出した。
私は研究者でもないし、時代の趨勢に、その時々に立ち止まる傍観者にすぎず、自分がその時何を感じ、何を読んだのか、振り返ってみたくなるときもある。BLMの運動は30年前の高揚した抵抗運動の記憶を呼び覚まし、捨ててしまったルイ子さんの本を思い出すことになった。
1992年、グアテマラの先住民、リゴベルタ・メンチュウがノーベル平和賞を受賞。グアテマラでは96年まで内戦が続き20万人が拷問、虐殺され、夫を返せ息子を返せとCONAVIGUAという女性の運動が起こり、私も遠巻きに支援したりした。国連では93年に「世界の先住民族の国際年」が宣言され、先住民の権利回復が実現し、明るい未来を予感させるものだった。91年に「インディオ・黒人・民衆の抵抗の五百年キャンペーン」の第2回大会でリゴベルタ・メンチュウは開会宣言で次のように述べている。
「今、何かが始まりかけています。そしてこの動きはわたしたちの形づくるものです。私たちはインディオでありたい。今日を生きるインディオ、そして明日を生きるインディオでありたい」(『「コロンブス」と闘い続ける人々—インディオ・黒人・民衆の抵抗の五百年』中米の人々と手をつなぐ会 大村書店 1992年)
コロンブスから500年。声をあげるのに、どんなに長い道のりだったろう。『インディアスの破壊についての簡潔な報告』(ラス・カサス 岩波新書 1976年)を読んだのは高校生のときだったろうか。書かれてから何百年もたっているのに、いまだに読み継がれているのは、その衝撃的な内容にあるのだろう。抵抗運動が起こる理由はこの本の中に十分ある。これが私の怒りの原点であった。
さて捨ててしまった『サンディーノの子どもたち』はサンディニスタ革命下のニカラグアの写真とルポ。人々が自治と自由を求めて起こしたサンディニスタ革命もアメリカ合衆国に後押しされた反革命勢力(コントラ)によって内戦が続いた。新自由主義によって中南米を支配したいアメリカにとって、革命は許しがたいものであった。73年のチリがそうであったように、中南米ではどこも同じ状況が起こっていた。この中で私が知ったのは「解放の神学」。神学者たちが社会正義のために立ち上がったのだ。 解放の神学の思想は世界に広がり、2001年にAttacの呼びかけで始まった「世界社会フォーラム」に影響を与えた。その運動の根底をなす「もう一つの世界は可能だ!」という考え方は、オキュパイや今繰り広げられている気候運動へとつながっているのだろう。「コロンブスから五百年」は新たな地球規模の価値観の変容を試みる大きな一歩だったのではないか。 サンディニスタとは何だったのか、私の中の一つの原点であったのに、ルイ子さんの本を自ら失った自分にそれを問う権利があるのか自問している。
さて、30年もたっているから、当時読んだ本の題名もほとんど忘れてしまったが、影響を受けた何冊かは記憶にしっかり残っている。まず何といっても『叛アメリカ史―隔離区からの風の証言』(豊浦志朗 筑摩書房 1989年)。豊浦志朗さんは船戸与一として有名ですが、これは彼が書いたルポルタージュ。白人ではなく、アメリカを先住民や黒人の立場から書いた。船戸与一といえば、『炎、流れる彼方』(集英社 1990年)でコントラを取り上げている。これも反米的。反帝国主義。中南米に関係ないが船戸さんの本で特に好きなのが『蝦夷地別件』(新潮社 1995年)。1789年に北海道で起きた「クナシリ・メナシの戦い」を題材にしている。これは和人によるアイヌの虐殺事件であるが、アイヌの歴史を小説にしたものは珍しい。船戸与一の小説はハードボイルドで分厚いのだけれど、面白いから止まらず読んでしまう。本棚をさがしたら、『砂のクロニクル』(毎日新聞社 1991年)が出てきた。これは中東の話だったような。分厚い。
もう一冊『陽と風の道標〜北南米大陸横断3万キロ』(戸井十月 講談社 1989年)。これも忘れられないが、本棚をさがしたら見つからない。処分したのかな。残念至極。表紙の裏に確かセンデロ・ルミノソの仕業による犬の死体がいくつもぶら下がっている写真があったような。記憶が正しければ。それで興味を持って買ったのが『センデロ・ルミノソ―ペルーの〈輝ける道〉』(現代企画室 1993年)。久しぶりに開いたら、釧路行きのJAS(日本エアシステム)の航空券の半券が出てきた。日本エアシステムもうないよね。
そうそう、『陽と風の道標』。細かいところははっきり覚えていないのだが、戸井さんがオートバイに乗って、アメリカ大陸を縦断しながら、出会った人々や情景をルポしたもの。そこから見えてくるのは、素朴に生きる人々の姿だ。社会の情勢に流されながら、貧困と闘う中南米の先住民。1993年に東京国立近代美術館でセバスチャン・サルガドの「人間の大地」を見て心を揺さぶられた。戸井さんのルポがひしひしと思い起こされたことを思い出した。
そういえば、戸井さんの本を読んでから何年後かに『キングズ・オブ・コカインーコロンビア・メデジン・カルテルの全貌』(草思社 1992年)という本を読んだ。もちろんカルテルの麻薬王たちがいかに悪い奴らであるか上下巻にわたって書き連ねているのであるが、『陽と風の道標』では、カルテルが麻薬で儲けたお金で貧困で喘ぐ人々を支えていたというくだりがあって、アメリカのジャーナリズムに疑問を持ったりして。
最後に今月の一冊にあげた『チリ 嵐にざわめく民衆の木』。これはクーデター後のチリを書いたもの。パブロ=ネルーダの詩がある。
見てくれ この木を
嵐にざわめく木だ 民衆の木だ
それは民衆の木だ
すべての民衆の木だ
自由の木 闘争の木
「コロンブスから五百年」以後も抵抗運動は続いている。
今月はゆっくり本を読んでいる時間がなく、30年前の「コロンブスから五百年」の当時のことを思い出して書いてみました。認識が間違っているところや忘却の彼方に行ってしまったこともあると思いますが、もし興味がある本があれば読んでみてください。また、もしよい本があったら紹介してください。最後に私の好きな曲を贈ります。聞いてみてください。「あなたはすべてを持って行ったが、風も太陽もあなたは買うことができないのですよ」。
https://www.youtube.com/watch?v=sGUz9ZNMucM
Vamos Caminando
歩きつづけていこう
*「週刊 本の発見」は毎週木曜日に掲載します。筆者は、大西赤人・志水博子・志真秀弘・菊池恵介・佐々木有美・根岸恵子、黒鉄好、加藤直樹、ほかです。
Created by staff01. Last modified on 2021-11-11 22:54:48 Copyright: Default
