
・レイバーフェスタ2025
・レイバーネットTV(12/10)
・あるくラジオ(11/1)
・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告
・ブッククラブ(12/13)
・シネクラブ(10/11)
・ねりまの会(6/28)
・フィールドワーク(6.1報告)
・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)
・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画
●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10)
●〔週刊 本の発見〕第416回(2025/12/25)
●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6)
●川柳「笑い茸」NO.164(2025/11/25)
●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)
●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14)
●「美術館めぐり」第18回(2025/12/22)
★カンパのお願い
■メディア系サイト
原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP
|
|
|
ログイン |
|
情報提供 |
|
|
|
Status: published View |

「街の本屋」が苦戦している
●「本を売る」という仕事−書店を歩く(長岡義幸 潮出版社)/評者=渡辺照子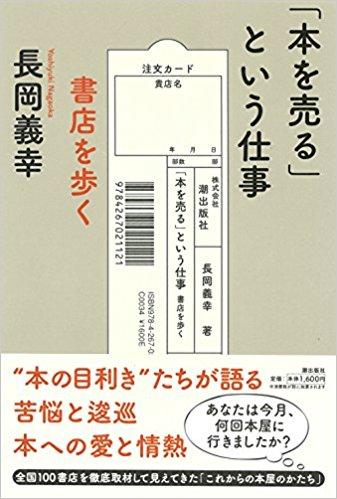
ところがそんな「街の本屋」が軒並み閉店している。地方都市の老舗、地域一番店の閉店ニュースも聞く。「閉店は寂しい」とコメントする人もいるが、それを思うなら本屋から注文をして購入すべきなのだ。アマゾンからではなく。と恨みつらみを言わせてもらってからやっと本題に入る。
本書は、書店経営をひとつのビジネスととらえる経済本ではない。よく見かける「エッジの効いたユニークな本や」「イマドキのブックカフェ」「リーディングカンパニーたる大型書店」にスポットを当てたものでもない。もっと生活に密着した「街の本屋」が主人公だ。著者が全国を行脚し、特に家族経営の小規模の100店舗もの書店を取材した文字通りの労作だ。著者の関心分野は表現の自由、子どもの権利に並び出版流通とあって、書店への愛と、地域での書店経営の人々への尊敬の念にあふれた好著だ。
再び言及するが、その「街の本屋」が苦戦している。本書によると2017年現在で新刊書店のない自治体は宮崎県串間市、茨城県つくばみらい市などを含む420市町村・行政区であり、全市町村・行政区の5分の1にもなるのだという。書店自体も1999年から17年間もの間で毎年500〜600店ずつなくなっているそうだ。なんともショッキングな数字ではないか。アマゾンが2000年に日本に上陸し、紀伊国屋書店等を大きく抜いて売り上げ日本一になってしまっているのも私は寂しい。がんばれ!リアル書店!負けるな!街の本屋!(これは余談だが、派遣業界との事業規模の比較をすると、かなり悲しい。派遣会社の業界1位のリクルートの売り上げ収益は今年、2兆840億円が見込まれるそうだ。片や出版業では、主要対象企業24社の売上高の合計は1兆1,112億円。規模が違う。)
*著者が愛した「街の本屋」
インクの匂い、紙のこすれる音、ページをめくる時の小さな風、本の精はそういったものの中から生まれるのだ。アマゾンでは、テーマや著者等を決めないと本が検索できない。だが、リアル書店では、自分の関心領域の及ばない本との思わぬ出会い、邂逅があるから世界が広がるぞ、楽しいぞ。
書棚にその書店の心意気を感じるときがある。パターン配本という、取次店が本の仕入れを決めてしまい、大型書店に優先的に売れ筋の本が配本される仕組みがある中で、そうした本屋はかなりがんばっている。著者はそのことを「棚で会話する」という。客の好みを先読みした本を並べてみたり、新しい切り口のテーマで多様な本を置いてみたり。「文脈棚」というらしいが、「本好きあるある」ネタで、私はにやりとする。
書店経営は、多品種少量で極めて利益率の低い商いだが、「街のインフラ」だという使命感や誇り、そして本が好き、というモチベーションが著者の行脚先である書店の経営者を支える。「最寄り型書店」と呼べるような、地域に人々にとってより身近な、現にある需要を満たすために奮闘する街の本屋に著者は心を惹かれている。「住民の読書環境を保証する生活基盤だ」というくだりにはぐっときた。その意味でも、特に東北大震災後の被災地の本屋の取材が胸を打つ。自分の住まいや家族さえも失い、被災者になった書店主が、悪戦苦闘しながら書店を再開する経緯には目が潤んだ。なんとか死を免れ、食べるものを確保した後、人間らしい暮らしには本が必要なのだ。復興は、国や行政ばかりがするものではない、市民自身が格闘して成し得るものだと私は思った。取材した先々の書店の写真も好ましい。丹精込めて並べた書棚を背に、飾らぬ表情の書店の人たちの誠実な人間性を感じる。そんな人たちが営む書店には人が集まる、絆が生まれる。読書自体は孤独な行為だが、つながりもできるものなのだ。その幸福な実例をいくつも本書で見出すことができる。本屋は客が創るものでもあるのだと思った。私の本への愛情は、より一層増した。
*「週刊 本の発見」は毎週木曜日に掲載します。筆者は、大西赤人・渡辺照子・志真秀弘・菊池恵介・佐々木有美・佐藤灯・金塚荒夫ほかです。
Created by staff01. Last modified on 2018-02-08 00:32:24 Copyright: Default


