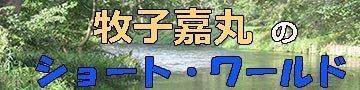・レイバーフェスタ2025
・レイバーネットTV(12/10)
・あるくラジオ(11/1)
・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告
・ブッククラブ(12/13)
・シネクラブ(10/11)
・ねりまの会(6/28)
・フィールドワーク(6.1報告)
・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)
・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画
●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10)
●〔週刊 本の発見〕第416回(2025/12/25)
●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6)
●川柳「笑い茸」NO.164(2025/11/25)
●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)
●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14)
●「美術館めぐり」第18回(2025/12/22)
★カンパのお願い
■メディア系サイト
原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP
|
|
|
ログイン |
|
情報提供 |
|
|
|
Status: published View |
第28回 2016年3月18日
「朝鮮半島と日本の詩人たち」を読む
今年2月7日の日曜日の朝のことを覚えていますか。NHKはいきなり国会討論会を中断して、朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮)のミサイル発射の臨時ニュースを待ってましたとばかり報道。他の民放各局もまるで臨戦態勢にでも入ったかのように一斉に垂れ流した。いったい、何が起こったんだと驚いた人がほとんどだろう。そう思わせるように放送しているんだから、あたりまえだ。今にもどこかからかミサイルが飛んできそうな恐怖感を植えつけることに成功したと、きっとほくそえんでいるのだろう。事前に国際機関に通知済みのロケット発射をミサイルだの、迎撃だのと出来もしないことをいって大騒ぎしている。そもそもミサイルとロケットはどうちがうのか。アメリカのや、日本の種子島から打ち上げたのはどうなんだ。もしこんな素朴な疑問を口にしたら、お前は北朝鮮のスパイか、在日か、それでも日本人か、と飛んでこないミサイルより恐ろしい非国民バッシングに遭わせられるだろう。北朝鮮のやっていることがいいなんて何ひとつ言ってなくても、このありさまだ。
昨年、北朝鮮を脱出した脱北者は2万8000人余りに達するという。核開発の犠牲者は北朝鮮の住民でもある。だからこそ、30万人もの米韓軍事挑発をいますぐ止めよと言いたい。同時にアベたちは北朝鮮の脅威を煽って、選挙に利用し、憲法改悪をたくらんでいる。武力で脅かしたり、恐怖や不安をいたずらにふりまいたりするのではなく、まずは誠意を持って相手の言い分を聞こう。
こんなとき朝鮮と日本の関係を冷静に考えるにふさわしい一冊の本が上梓された。卞宰洙(ピョン・ジェス)さんの「朝鮮半島と日本の詩人たち」という、日本の近現代詩人90人から日朝の歴史と交流を描いた詩を時代別にまとめた労作である。高村光太郎・萩原朔太郎から宮沢賢治・中原中也、またプロレタリア詩人の中野重治や小熊秀雄、現代詩人では辻井喬・大岡信・吉野弘など多くの詩人の朝鮮民族と文化・歴史への敬愛と友好をこめたすぐれた詩が採録されている。
著者は言う。詩人は優れた知性の感受性の持ち主であり、また時代の警鐘者でもある。これらの詩人が朝鮮および朝鮮人への深い理解と正しい同情を示したことは日本の知性人を誇るべき存在にしている、と。しかし、残念ながらその知性を曇らせ、侵略戦争を聖戦と見誤った詩人もいる。高村光太郎・草野心平・室生犀星・斎藤茂吉らの戦争協力や戦時転向した壺井繁次の戦争賛美についてもきちんとふれてあるのは公正であり、見識である。
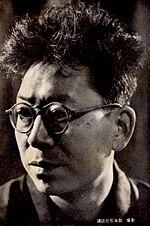

ここでは有名詩人ばかりではなく、濱口國雄や吉田欣一、また磐城葦彦などいわゆる労働者詩人の詩が取り上げられていることも付け加えておきたい。磐城氏は現在「労働者文学」の代表であり、現役の詩人として活躍されている。詩人がみな詩集をもっているわけではない。サークル誌や同人誌に書いたままのものもある。そのような詩まで目を通された著者の功績を多としたい。
この政治的激動期に詩集を手にとる暇がないのはお互い様である。しかし、またこんな人間性をないがしろにする状況だからこそ、最高の知性人の韻文にふれたいものだ。一冊で90篇もの詩が読めるのもありがたい。ヘイトスピーチへの強烈なカウンターにもなるだろうし、まず何よりも自身が心豊かにもなるだろう。
(本書は『スペース伽耶(かや)』から2月に発行)
Created by staff01. Last modified on 2016-03-18 10:05:46 Copyright: Default