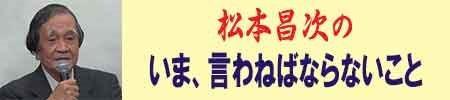第三回 2013/6/1(毎月1日発行)
「村上春樹」異論 松本昌次(編集者・影書房)
前回、NHKがテレビで今も流しつづける『花は咲く』を、わたしは、戦争中に歌われた『海行かば』と銅貨の裏表のような歌で、希望の涙で被災者の苦難を誤魔化していると批判した。ところでその後、辺見庸氏が、毎日新聞5月9日付「特集ワイド」で、『花は咲く』を同じように戦争中はやった『とんとんとんからりんと隣組』と一緒の「気持ち悪い」歌と評し、福島などの「非人間的実相を歌で美化してごまかし……被災者は耐え難い状況を耐えられると思わされている」と語っているのを読み、さすがとわが意を得た思いだった。
しかし、問題はこれから先にある。近く出版される本の中で、辺見氏が『花は咲く』を揶揄(やゆ)したところ、編集者が「それだけはどうしてもダメだ」「みんながノーギャラでやってて、辺見さんも自作をちゃかされたら嫌でしょ」と言ったというのである。辺見氏は「もう目をぱちくりする」ばかりだったが、わたしも同様、目をぱちくりしつつ、自由に書くこともできない出版界の頽廃もとうとうここまできたかと、無残な思いにとらわれた。
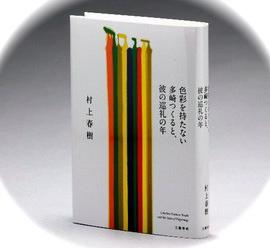
村上氏のこれ迄の作家としての業績は世界的に知られており、わたしがとやかくいう筋合ではないが、村上氏の最近のいくつかの言動には深い違和感を覚える。先日のボストン・マラソンで起った爆破事件での3人の死者を悼み、米ニューヨーカー誌(デジタル版)に村上氏が寄稿したことが新聞で報じられていた(朝日・5月5日)。いうまでもなく、死者を悼むことはいい。しかし、村上氏は、爆破を実行し生き残った青年が、イラク戦争での米国の侵略行為への報復と告白した新聞の小さな記事もご存知だろう。だから爆破が許されるわけではないが、戦争での女・こどもなど非戦闘員を多数含むイラク人約12万人の死者に対する追悼、同時に米国に対する抗議の言葉もあってしかるべきではないか。ボストン・マラソンを復活させて、3人の死者たち、傷ついた人たちを癒したいというが、数多くのイラクでの犠牲者たちはそれで癒されるだろうか。
また、去る5月6日、村上氏は、京都大学で河合隼雄物語賞・学芸賞創設を記念して講演したが、冒頭、「僕はごく普通の生活を送っている普通の人間」などと語っている。しかしかつて「エルサレム賞」の受賞で、最も政治的に緊迫しているイスラエルまで出かけ、有名なスピーチ『壁と卵』を行い、「壁」を曖昧な「システム」と称し、みずからは固い壁にぶつかって壊れる「卵」と言いながら、堂々と「壁」の側から賞金を貰ってくる人が、果たして「普通の人間」だろうか。明らかに「壁」に加担しているではないか。エルサレム賞はノーベル文学賞の登竜門といわれる。率直に「賞」が欲しかったというのが、「普通の人間」のありようである。ちなみに、最近、「車椅子の天才理論物理学者」スティーブン・ホーキング博士は、イスラエルのパレスチナ人に対する対応に抗議し、エルサレムで6月に開かれる国際会議への出席を拒否したという。
できれば、新著は予測どおり100万部売れてほしいものである。売れ残って断裁などで廃棄処分されたらまさに資源の無駄である。尤も文壇を支える人たちが、応援の大合唱をくり拡げるだろうから、危惧することもあるまいが。
Created by staff01. Last modified on 2013-05-30 20:32:21 Copyright: Default