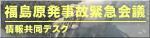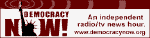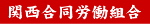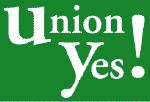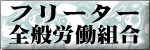・レイバーフェスタ2025
・レイバーネットTV(12/10)
・あるくラジオ(11/1)
・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告
・ブッククラブ(12/13)
・シネクラブ(10/11)
・ねりまの会(6/28)
・フィールドワーク(6.1報告)
・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)
・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画
●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10)
●〔週刊 本の発見〕第416回(2025/12/25)
●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6)
●川柳「笑い茸」NO.164(2025/11/25)
●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)
●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14)
●「美術館めぐり」第18回(2025/12/22)
★カンパのお願い
■メディア系サイト
原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP
|
|
|
ログイン |
|
情報提供 |
|
|
|
Status: published View |
第10回・2010年6月19日掲載
「罪と罰」
今、東京の国立新美術館でオルセー美術館「ポスト印象派」展を開催中だが、大改装中のパリのオルセー美術館では3月中旬から6月末まで、「罪と罰」と題する独創的な企画展が行われている。
発案者は元法務大臣のロベール・バダンテール。1981年の9月、ミッテラン大統領の左翼政権が成立して4か月後に、フランスで死刑の廃止を実現させた人物だ。長年、死刑廃止のために弁護士として闘い、すべての人間社会に存在する刑罰を定める法を研究してきた彼は、「罪と罰」という普遍的な現象は、法律や慣習からだけは見えてこないという。ギリシア神話や聖書から現代小説まで、文学はもちろん、罪と罰のテーマを頻繁に描いてきた。では、造形美術がどのようにそれを表現してきたか、社会の変遷に照らし合わせてみたい、というのがバダンテールの関心だった。
彼の提案に美術評論家のジャン・クレールが賛同し、19世紀(正確には19世紀後半〜第一次大戦)の美術を展示するオルセー美術館での企画展が練られた。大革命から第二次大戦前夜1939年にいたる150年のあいだ、フランスでは産業革命とブルジョワ社会の発展によって、アートの表現様式は大きく変化した。政治面でも、帝政2回、王政2回、共和政3回と政体が頻繁に変わったが、法制という面では大きな変革はなかったとバダンテールは指摘する。フランス大革命時に、従来の死刑がもたらす身体的苦しみを和らげるための人道的配慮から導入されたギロチン、徒刑、監獄という刑罰の三形態は、法が多少緩和される傾向にあっても存続しつづけたのだ。展覧会には、1977年まで死刑に使われたギロチンの実物も展示された。
カインの兄弟殺害の表象(西欧における殺人の原点)から始まる展示には、ギュスターヴ・モロー、ジェリコ、ゴヤ、ドガ、ムンク、マグリット、オットー・ディックスなどの作品が、さまざまなテーマごとに集められた。死刑廃止論者だったヴィクトル・ユーゴーの絵画作品(写真下)や、「強かん」というタイトルのドガの油絵など、あまり知られていない作品も見られて、興味深い。
ヴィクトル・ユーゴーが『死刑囚最後の日』を書いたのは1829年。ギロチンによる処刑を何度か目撃して、「死刑囚が咎められている行為(殺人)を社会が平然と行っている」ことに憤慨したからだった。19世紀、法制は政治犯の死刑の廃止、情状酌量の適用、精神病者への配慮など、刑罰を緩和する方向に向かった。しかし、ミシェル・フーコーが『監獄の誕生ーー監視と処罰』で指摘したように、公開の「見せ物」だった処罰は近代では公衆には見えない場所で行われ、合理性・経済性などにもとづいた犯罪者の管理が進む。展覧会では、フーコーが紹介したイギリスの思想家、ジェレミー・ベンサムによる「パノプティコン」の監獄の構想も展示されている。円形の建物の中心にすえた塔に囚人からは見えない監視員を設置し、常に監視されているという認識(自己規制)によって、品行方正で従順な行動を促そうという案だ。パンプティコンの原理は監獄にかぎらず、病院や学校、仕事場にも適用できる。犯罪のない社会をめざしたユートピア思想だが、思えば21世紀の今、テクノロジーによって「こちらからは見えない権力による大勢の監視」にもとづく管理社会は着々と進行している。
19世紀のヨーロッパではまた、科学と実証主義の発達につれて、犯罪を論理的に解析し、予防しようという考え方が広まった。骨相学や犯罪人類学は、犯罪者に特有の身体的・精神的特徴があるのではないかという仮説を実証しようとしたもので、進化論に影響を受けたイタリアのロンブローゾは、犯罪者の特徴は原始人のそれが隔世遺伝(先祖返り)した先天性のものだとする「生来的犯罪人説」を発表した。犯罪人の先天性という考え方は、当時の社会に大きなインパクトを与えた。展覧会の「犯罪と科学」のスペースには、犯罪人の脳、身体特徴を測定した器具や写真なども展示されている。警察・司法にかぎらず、美術家や文学者もこの「生来的犯罪人説」に影響を受けた。ドガの作品に「十四歳の踊り子」という題の彫刻があるが、彼はモデルのデッサンをもとにした彫刻に、「犯罪者の身体的特徴」と当時考えられていた要素(突き出た顎、後ろにそった額など)を加えたのだそうだ。
ロンブローゾの理論は後に、優性思想や「頽廃芸術」の概念を生み出し、人種差別思想に格好の「科学的」根拠を与えた。博愛の観点から犯罪や狂気の研究にとりくんだユダヤ系科学者の理論が、究極的にはナチスの人種主義、精神病患者の抹殺やユダヤ、ロマ民族絶滅計画に結びつくとは、なんとも悲劇的だ。しかし、だからこそ、何が誤っていたのかを考える意味があるだろう。ロンブローゾは犯罪の原因を人間のおかれた状況、社会環境やそれまでの人生にではなく、先天性に求めた。先天性信仰は、「先天的に劣悪なものは改良できないから、排除するしかない」という排除の思想につながりやすい。また、植物・動物学などが使うデータの分類法を人間に適用すると、不毛なコレクションが蓄積されるばかりでなく、悪用されかねない。科学は純粋な知識として存在するのではなく、常に社会(権力)の要求と密接に関係をもっているのだ。
バダンテール元法務大臣がこの展覧会で「犯罪と科学」のテーマをとりあげたのは、現在のフランスで、この先天性信仰が復活してきているからだ。サルコジ政権は2008年に、危険な囚人の予防拘禁(刑期満了後の拘禁)を定める法律をつくり、「危険人物」という19世紀の概念を復活させた。また、市民の大規模な署名運動のおかげで実現されなかったが、内務大臣の時代にサルコジは、3歳の子どもに「非行予防」のための心理テストを行う案を主張した。アメリカ合衆国には、遺伝学とMRI(核磁気共鳴画像法)を根拠に子どもの行動障害を説明し、薬品でそれを治療する「専門家」が大勢いるが、フランスでもそうした考え方が力を得てきているらしい。
凶悪な犯罪が起きるたび、サルコジはさらに厳しい法を新たにつくらせ、「犯罪と危険を一掃する」といきまく。むろん、犯罪はなくならない。悪を自分の外にある異物だと考え、排除しようとする思考がいきつくところは、皆殺しだけだ。いま市民、とりわけ刑法をつくる人々に必要なのは、なぜ人間社会では常に犯罪が起きるのか、それに対する刑罰がどのように変化してきたか、豊富な判例や文学、芸術に描かれてきた「罪と罰」について、冷静に考えることではないだろうか。バダンテール元法務大臣は、そんな思いもこめて、この展覧会を発案したのかもしれない。
2010.6.18 飛幡祐規(たかはたゆうき)
写真=ヴィクトル・ユーゴー「ジュスティシア」1857年
(c) Paris, maison Victor Hugo / Roger-Viollet
Created bystaff01. Created on 2010-06-19 16:34:29 / Last modified on 2010-06-19 17:23:45 Copyright: Default