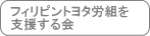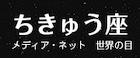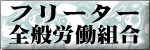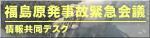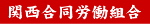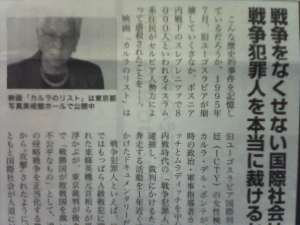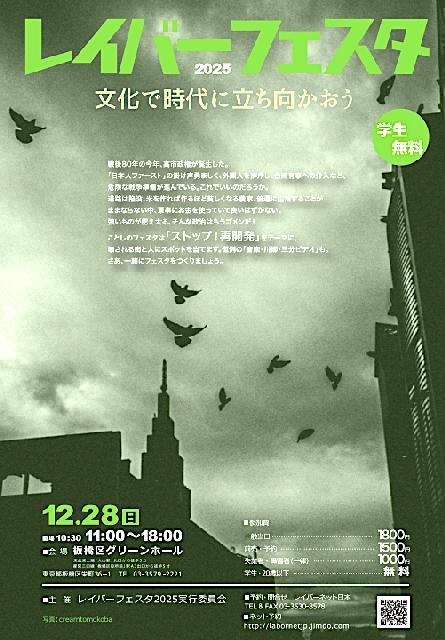
■サブチャンネル
・フェスタ投句募集中
・映画祭報告(7/27)
・レイバーネットTV(12/10)
・あるくラジオ(11/1)
・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告
・ブッククラブ(12/13)
・シネクラブ(10/11)
・ねりまの会(6/28)
・フィールドワーク(6.1報告)
・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)
・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画
●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10)
●〔週刊 本の発見〕第414回(2025/12/4)
●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6)
●川柳「笑い茸」NO.164(2025/11/25)
●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)
●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14)
●「美術館めぐり」第17回(2025/11/24)
★カンパのお願い
■メディア系サイト
原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP
|
|
|
ログイン |
|
情報提供 |
|
|
|
Status: published View |
●映画「カルラのリスト」
戦争をなくせない国際社会は
戦争犯罪人を本当に裁けるか
こんな歴史的事件を記憶しているだろうか。1995年7月、旧ユーゴスラビアが崩 壊していくさなか、ボスニア内戦下のスレブレニツァで8000人といわれるイスラム 系住民がセルビア人勢力によって虐殺されたことを―。
映画「カルラのリスト」は旧ユーゴスラビア国際刑事法廷(ICTY)の女性検察官 カルラ・デル・ポンテが、当時の政治・軍事指導者カラジッチとムラディッチを中心に 、内戦時代の「戦争犯罪人」を逮捕し、裁判にかけるために奔走する活動を1年近く追 いかけたドキュメンタリーだ。
戦争犯罪人といえば、日本ではもっぱらA級戦犯に問われた東條英機元首相らが思い 浮かぶが、東京裁判が後々まで「戦勝国が敗戦国を裁いた不公平なもの」として、過去 の侵略戦争を正当化する勢力から“攻撃”されたように、もともと国際社会が人道に対 する罪を裁く仕組みは長らくなかった。それが整えられ始めたのは、やっとこ冷戦が終 結してからのことだ。
カルラはスイスの司法長官から6年前にICTY検事に任命され、隠れ潜む大物戦犯 を捜し続けている。が、容疑者の引き渡しを拒むなど、各国の非協力的姿勢と相まって 捜査は難航を極めている。
映画では、カルラがムラディッチの身柄引き渡しを求めてセルビア首脳らと交渉する シーンや、その交渉時にセルビア人を迫害したクロアチアのゴトヴィナ将軍がスペイン で拘束されるドラマチックなシーンなどが見どころだ。
画面いっぱいに広がる墓標の列、いまだ身元不明の大量の遺体……といった無残な光 景、家族を失った母親たちの悲しみにも光を当てる。その一人の「大虐殺を、たった二 人の男に責任を負わせるなんて……」という言葉は重い。
なお映画は、日本が10月にICTYの後身ともいうべき国際刑事裁判所(03年発足) にようやく加盟したことで緊急公開となった。
*「サンデー毎日」07年11月25日号所収
――――――――――――――――――――――
●映画「サラエボの花」
あからさまに映さない「過去」
それだけに切なく残る「傷痕」
旧ユーゴ連邦の解体に伴い、多民族国だったボスニアで内戦が勃発すると「民族浄化 」が横行し、一説には「2万人の女性がレイプされた」という。それも収容所に入れら れ、繰り返し、大勢の男たちから集団で辱められた。
死者20万人、難民・避難民は200万人。第二次大戦以降、ヨーロッパで起きた最大 ・最悪の「戦争」である。 女性監督ヤスミラ・ジュバニッチの「サラエボの花」は十余年後の今なお、心に傷を 負う女性とその娘に焦点を当てたドラマだ。といっても、映る街並みに戦争の影はなく 、生々しい回想シーンもない。
主人公のエスマはムスリム人で、12歳の娘サラと暮らしている。生計を補うためナイ トクラブのウエートレスとしてかいがいしく働く。そんな彼女が時折、異常な反応を見 せる。ふざけた娘に馬乗りにされたとき、バスの中で胸毛の濃い男を見かけたとき…… エスマは苦しそうにあえぎ、駆け出す。それによって、おぞましい過去の傷痕に苦しん でいることがわかる。
一方、父のいない娘は、周囲に父は「殉教者」だったと語り、同じ境遇の少年と仲よ くなっていく。誇りである父のことをもっと知ろうとして、母といさかいになる。母娘 の葛藤の中に、戦争の真実があらわになってくる。
原題の「グルバビッツァ」はセルビア人に制圧されたムスリム人地区の名だ。ジュバ ニッチ監督はインタビューで「セックスは戦争戦略の一つ」で「女性に屈辱を与える手 段」として意識的に利用されたと話す。それまでのよき隣人が突然牙をむいて襲うとい う倒錯―それが戦争だ。
が、映画はそれでも懸命に生きていく母娘と、それを助ける女性たちの姿を通して、 民族の“壁”を超えた未来も予感させる。エスマを熱演したミリャナ・カラノヴィッチ はセルビア人の女優。男性も必見だ。
*「サンデー毎日」07年12月9日号所収
Created bystaff01. Created on 2007-12-05 14:24:01 / Last modified on 2007-12-05 14:26:59 Copyright: Default