
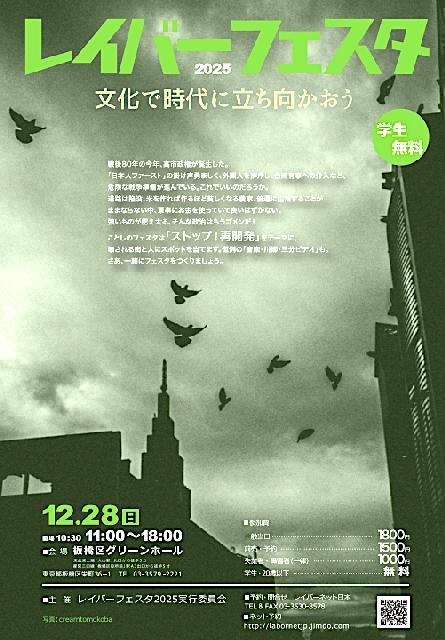
■サブチャンネル
・映画祭報告(7/27)
・レイバーネットTV(12/10)
・あるくラジオ(11/1)
・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告
・ブッククラブ(12/13)
・シネクラブ(10/11)
・ねりまの会(6/28)
・フィールドワーク(6.1報告)
・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)
・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画
●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10)
●〔週刊 本の発見〕第415回(2025/12/18)
●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6)
●川柳「笑い茸」NO.164(2025/11/25)
●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)
●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14)
●「美術館めぐり」第17回(2025/11/24)
★カンパのお願い
■メディア系サイト
原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP
|
|
|
ログイン |
|
情報提供 |
|
|
|
Status: published View |

黒人の肉体をもって生きること
●タナハシ・コーツ『世界と僕のあいだに』 慶應義塾大学出版会、2017年/評者:菊池恵介
タナハシ・コーツは1975年にメリーランド州のボルチモアで生まれた。失業、貧困、ドラッグが蔓延する黒人ゲットーで育った彼にとって「一番の関心は、肉体の安全だった」。路上での恐喝、ギャングの抗争、警官の職務質問や発砲など、偏在する暴力をいかに切り抜けるかが日々の課題だった。「住んでいる地域で生き延び、自分の肉体を守るためには、僕はうなずきかたや握手の仕方という基本的な要素からなる、もう一つの言語を身につけた。行ってはいけないブロックのリストはそらで言えた。〈喧嘩日和〉のにおいや感触を学んだ。(…)ストリートの法ってのは、自分の肉体を安全に守るためには絶対に欠かせないものだった」。
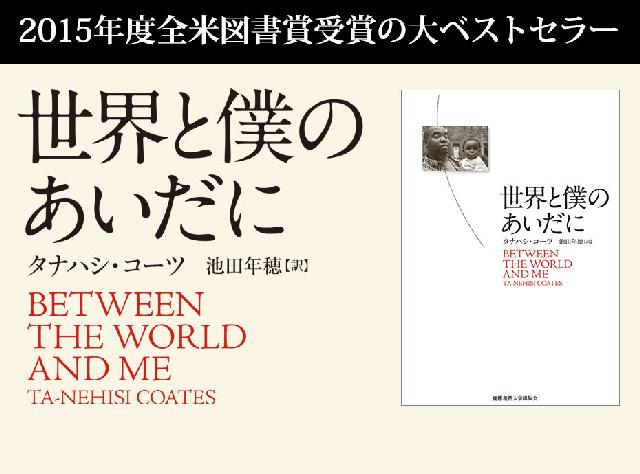
この暴力的な世界を抜け出す糸口となったのが、母親による読み書きの指導であり、父親の蔵書だった。かつてブラック・パンサー党の支部長であり、ハワード大学図書館の司書だった父は、黒人運動史に関するあらゆる本を収集していた。少年時代のコーツは、その蔵書を貪るように読み、怒りを言葉に変える術を学んだ。とりわけ傾倒したのが、文化による政治的・精神的なルネッサンスを訴えたマルコムXの思想である。
1993年、コーツは黒人教育の「メッカ」として名高いハワード大学に入学し、アメリカだけでなく、世界中から集まるアフリカン・ディアスポラに遭遇する。西ボルチモアの黒人ゲットーしか知らず、ひたすら恐怖と劣等感を植え付けられてきた彼にとって、それはまさに再生の日々となった。「黒人の世界が僕の目の前で広がっていた。そしていまや僕には、黒人の世界は、自分たちを白人だと信じている者たちの世界の単なる陰画(ネガ)ではないということが見て取れた」。また、そこで「黒人の美しさ」に目覚め、幾つかの恋も経験する。やがて大学を中退したコーツは、妻に付き添ってニューヨークに移住し、作家への困難な道を歩みだす。
* * *
『世界と僕のあいだに』を読んで印象深いのは、白人と黒人の現実認識の著しいギャップだ。奴隷制の末裔たちが絶えず暴力の予感に怯え、身構えて生きているのに対し、白人たちは「ドリーム」の中で暮らしている。彼らは強者として黒人たちを踏みつけながら、弱者に対して非暴力を要求する。奴隷制以来の収奪の歴史を忘却していることも、白人世界の特徴だ。「忘れるのは、この国の習慣で、〈ドリーム〉のもうひとつの必須要素なんだ。連中は、奴隷制により、自分たちを富ませた略奪の規模をもう忘れている。一世紀にわたって黒人から投票権を奪ってきたテロルをもう忘れている。美しい郊外を自分たちに割り当てた分離主義の住宅政策をもう忘れている」。
コーツも子供の頃、テレビ・ドラマに登場する白人中流層の生活に憧れた。きれいな芝生のある、閑静な郊外の一軒家に住み、庭の木の上にツリー・ハウスを造る…。だがそんな選択肢は一度もなかった。なぜなら、その「ドリーム」は、300年以上にわたる黒人収奪の歴史の上に成り立っているからだ。「僕たち黒人がこの国で奴隷にされていた年月が自由になってからの年月より長いことを絶対に忘れてはいけない」とコーツは息子に語る。その現実を忘却し、白人の「ドリーム」にうつつを抜かせば、必ずや痛いしっぺ返しを喰らうことになるだろう。
オバマ大統領の誕生は、「ポスト人種主義」の時代の到来として国内外で歓迎された。だが、警官による黒人の射殺事件の頻発は、その幻想を完膚なきまでに打ち砕いた。このトラウマ的な現実を黒人としてどう受け止めるべきか? その問いに鮮烈な言葉で答えたのが、当時39歳のタナハシ・コーツだった。『世界と僕のあいだに』が映し出す白人世界と黒人世界のギャップを、日本のマジョリティとマイノリティの関係性に置き換えてみると、一体何が見えてくるだろうか。そんなことも考えつつ、彼のメッセージを受け止める必要があるだろう
————————————————————————————————————
以下、冒頭部分からの引用:
僕は15歳になろうとするお前にこの手紙を書いている。なぜかと言えば、今年エリック・ガーナーがタバコを売ったために窒息死させられたのをお前が見たからだ。レニーシャ・マクブライドが助けを求めたために撃たれたことも、ジョン・クロフォードがデパートで商品をひやかしていたために撃たれたことも、もう知っているからだ。それから、制服を着た男たちがパトカーで通り過ぎた際にタミール・ライスを殺害したのも見たね。彼らが保護すると宣言したはずの12歳の子供をだよ。それから同じ制服を着た男たちが、誰かのおばさんにあたるマーリン・ピノックを道端で何度も拳で殴ったのも、すでに見ている。(…)お前の国の警察はお前の肉体を破壊する権限を与えられていることも知っている。
あれは、マイケル・ブラウンを殺害した男たちが釈放されることをお前が知った週だったね。(…)誰かがいずれ罰されるとは、僕は期待していなかった。けれどお前は若く、まだ信じていた。お前はあの晩、午後11時まで起きていて、起訴が発表されるのを待っていた。そして逆に起訴しないとの発表が行われたとき、お前は《もういかなかきゃ》と言って自分の部屋に引っ込み、やがてお前の泣き声が聞こえた。ぼくは五分後にお前の部屋に行ったが、抱きしめてもやらなかったし、慰めてもやらなかった。お前を慰めるのは間違っていると思ったからだ。大丈夫だと言ってやらなかったのは、大丈夫だなんぞと本心で思ったことが一度もなかったからだ。お前に伝えたのは、お前のおじいちゃん、おばあちゃんが僕に伝えようとしたことだった。これがお前の国なんだよ。これがお前の世界なんだよ。これがお前の肉体なんだよ。だからお前は、その状況のなかで生きていく方法を見つけなければならない。
*「週刊 本の発見」は毎週木曜日に掲載します。筆者は、大西赤人・渡辺照子・志真秀弘・菊池恵介・佐々木有美・佐藤灯・金塚荒夫ほかです。
Created by staff01. Last modified on 2018-04-26 11:14:46 Copyright: Default

