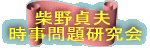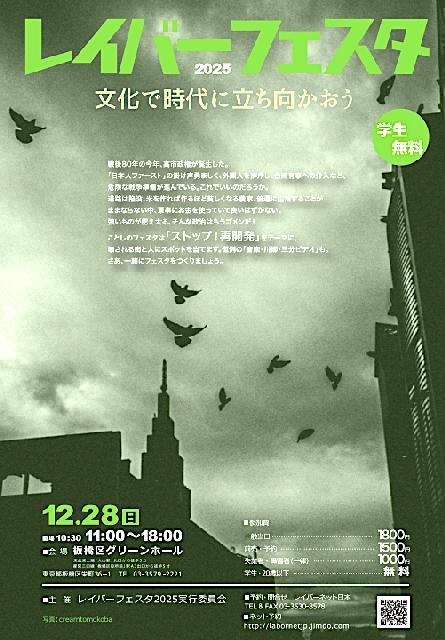
■サブチャンネル
・映画祭報告(7/27)
・レイバーネットTV(12/10)
・あるくラジオ(11/1)
・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告
・ブッククラブ(12/13)
・シネクラブ(10/11)
・ねりまの会(6/28)
・フィールドワーク(6.1報告)
・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)
・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画
●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10)
●〔週刊 本の発見〕第415回(2025/12/18)
●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6)
●川柳「笑い茸」NO.164(2025/11/25)
●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)
●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14)
●「美術館めぐり」第18回(2025/12/22)
★カンパのお願い
■メディア系サイト
原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP
|
|
|
ログイン |
|
情報提供 |
|
|
|
Status: published View |
●木下昌明のWEB版・映画批評『出草之歌』(2006年6月28日掲載)
「魂を返せ」―反靖国のたたかい
『出草之歌』について
木下 昌明
月刊「東京」2006年7月号所収
昨年のベストセラーになった高橋哲哉の『靖国問題』(ちくま新書)をひもとくと、高橋は冒頭で、靖国に対する二つの異なる「感情」を対置している。一つは日本人で、戦場で亡くなった兵士の遺族の感情、もう一つは、かつて日本の植民地にあって兵士にしたてられ、戦死したアジアの人々の遺族感情である。この二つの感情は互いに相いないか、東条英機らの戦犯が合祀され、首相が参拝するようになってから、それからいっそう際立つものとなった。そのなかにアジアの人々の遺族感情を代表する典型例として台湾立法院の委員(日本でいう国会議員)のひとり高金素梅を中心にした台湾原住民による「祖霊奪還」運動がある。それは第二次大戦下、日本軍が多くの原住民の若者たちを「高砂義勇隊」にしたてて戦死させた兵士を、戦後になって無断で靖国神社にまつっている――そのことに反対して神社側に抗議、裁判でたたかっているもの。高橋は、この運動を一つのよりどころ(モチーフ)にして、『靖国問題』の執筆にあたったことが一読して理解できる。
ところが、わたしがこれから批評しようと思う『出草之歌──台湾原住民の吶喊 背山一戦』というドキュメンタリー映画も、高金素梅らのたたかいに密着し、高橋が靖国批判のてことしたかれらの「感情」をあぶり出していて興味ぶかい。実は、この映画も、NDU日本ドキュメンタリストユニオンの井上修撮影・編集とあるように、高橋と同じく日本の側からつくったものである。しかし、高橋と違って、井上は台湾の現地におもむき、かれらの生活に深く入り込み、そこからかれらの靖国に対する批判の「感情」を掘り起こしているので、日本人でもその感情により共感できるものとなっている。つまり映画は、反靖国のたたかいを中心にすえているものの狩猟民族だったかれらの生活史やそこから生まれた歌や踊りや風俗などもとらえていて、それがたたかいに奥行きを与えている。
「原住民」といえば、日本では、かつて「土人」「蕃人」とよんでいたように一種の侮蔑的な意味あいがふくまれていたが、ここでのかれらは、台湾に渡ってきた人々ではなく、元からそこに住んでいたものという意味の誇りをこめて用いられている。そこでかれらの母体となる組織名を「原住民族部落工作隊」と日本語の漢字で命名しているわけだ。
それにしても台湾は、世界史のはざまで翻弄されて、実に複雑な成りたちをしている。それがこの映画をみていて改めて痛感させられた。というのも、一九四九年から八七年にかけて蒋介石(とその息子)のひきいる中国国民党によって戒厳令が敷かれていたことで台湾は鎖国状態にあり、内情を知ることができなかった。それゆえに関心も起きなかったが、侯孝賢の『童年往事』(八五年)や『非情城市』(八九年)などみるようになってからがぜん興味をいだくようになってきた。
『竜年往事』では、日本の植民地時代の日本式家屋に日本人に代わって国民党の人々が住みつくようになったこと、また『非情城市』では、台湾に戦前から住んでいる中国渡来の人々を「本省人」、戦後中国から逃れてきた国民党の人々を「外省人」とよび、前者が後者によって弾圧・虐殺され、台湾を支配統治されて、両者のあいだにはずっと差別やしこりが残っていたことなど知ることができた。こういった台湾史を知るうえで、侯の映画との出会いは大きかった。それによって見知らぬ国のふつうの人々の生き方をとおしてその国の内情が手に取るようにわかってきたからだ。
ところが、『出草之歌』をみると、さらに歴史的政治的に複雑な台湾社会の相貌がみえてくる。それは本省人よりも前に住んでいた原住民のいっそう差別された境遇である。高金素梅が一枚の絵をみせるシーンがある。絵は一匹の蛇がくねくねと上から下にのびていて、その尻尾から順に国旗が敷かれている。オランダ、スペイン、メキシコ、清、日本、中華民国の旗で、これらの国に次々と支配された表示である。このシンボリックな絵から原住民の抑圧された歴史がのぞきみえるが、かれらの日常会話もまたチャンポンで、日本語がポンポン飛びだしてくるのには驚かされる。また彼女は、一枚の写真を掲げ、植民地支配で日本が一番ひどかったことを説明する。写真は、日本の将校が原住民の首を斬り落とした瞬間のものだ。彼女は、どうして我々を殺した人と一緒に靖国にまつられなければならないのか、とその不条理を問う。この時の彼女の表情はきぜんとしていた。
では、高金素梅とは何者か。映画はトップからラストまで、ドラマのヒロインのように彼女を追いかけ、その言動に光をあてている。特に、トップの方で、彼女が昔の原住民衣装をまとい、頭髪はバンダナで締め、顔には帯状の刺青をほどこし、靖国の神社本殿に向かっていくシーンは印象深い。彼女はカメラ慣れしていてカメラを向けられても自然にふるまっている。それもそのはず、元女優であり歌手でもあった。そのうえに台湾立法院の委員で、原住民を代表する政治家である。わたしは、彼女が靖国裁判で来日の折、テレビのニュースで一度みたことがあるが、その事情についてよく知らなかった。それがこうして映画でみると端整できりりとしたその美しい顔にみとれてしまうが、彼女の発言も明晰で説得力にとんでいた。年齢は、三〇代後半か。彼女は、母が原住民のタイヤル族で父が漢族のハーフである。また数年前に肝臓がんにかかり手術したもののいつ再発するか分からないという。この病気が、彼女に女優から政治家へと転身させたのであろう。彼女はもう一つチワス・アリという原住民名をもっていて、それが原住民の歴史を学び、かれらの先頭に立ってたたかうなかでもう一つの名を告白したものといえよう。わたしは、“原住民のジャンヌ・ダルク”だと思った。
つぎに、この映画は、チラシのうたい文句にあるように、「音楽ドキュメンタリー」でもある。原住民は活動の一環として音楽グループ「飛魚雲豹音楽工団」を結成し、舞台で、広場で、街頭で、自分たちのたたかいを鼓舞する武器として歌をうたっている。歌の文化が政治活動と一体となってたたかう主体の活力源になっている。なかでも印象深いのは、「出草」と「生命の歌」の二つの歌だ。これらは古くから歌いつがれたもので、「出草」は首狩り族の時代からの出陣歌を元にしている。それはまるで狼が月に吠えているかのように雄々しく力強い。かれらは腰の蛮刀を歌に変えて、素手で歌でたたかいにいどむ。また、「生命の歌」は、朗々と歌われながらもどこか哀切である。映画はこのメロディーとともにかれらの住む山岳地帯や辺境の風物を映しとっていく。その南国のエキゾチックな光景にもわたしはみとれた。
そんななかで、いちばん刺激的だったのは、中核とする工作家の活動が決して少数民族としてのナショナリズムに陥っていないこと。かれらの掲げる運動方針は。台湾での原住民への差別や抑圧をなくし、人間としての権利を回復し、尊厳を取り戻すことにある。これに共感できるものであればだれもが参加できるという。しかもその最終目標は――この運動の中心メンバーの一人である漢族の張俊傑がのべているように――「拡張や略奪によって支えられている資本主義」ではなく、「階級の平等や民族の平等を保障する社会主義」をめざすところにある。こういう発言からわたしは唐突に「コミュニズム」とは、富の公正を分配ではなく、貧困の公正な分配である」というベルトルト・ブレヒトの言葉を想起する。張もまた、おそらく、「貧困の公正な分配」を根っこにすえて語っているのだろう。わたしは、かれらが狭い原住民主義に陥らずに遠大な世界観でたたかっていることに何よりもひかれた。それは反清国一つとっても、単に魂の奪還ではなく、そのたたかいを通して日本が軍国主義へとたどりつつあることへの、かれらの立場からの異議申し立てであること――それがわかったことだ。
戦時中、日本が台湾を支配していた時代、原住民(タイヤル族)の生活を描いた清水宏監督、李香蘭(山口淑子)主演の映画『サヨンの鐘』(四三年)がつくられた。わたしはこの映画を一〇何年か前にみたことがあるが、そこでのかれらは「高砂族」とよばれ、若者は軍事訓練をうけ、次々に出征していき、それをヒロインのサヨンたちが「海ゆかば」や「台湾軍の歌」をうたって見送るものだった。
その点で、この『出草之歌』は、日本映画が描いた原住民世界がいかに欺瞞にみちたものであったかを思い知らせてくれる。しかしである。そうはいっても、このなかでも、一人の日焼けした老人がカタコトの日本語で「オオカワミツノリ」という自分の日本名を名のり、……勝ってくるぞと勇ましく誓って国を出たからは手柄立てずに死なりょうか……と軍歌をとうとうとうたってみせるシーンが出てくる(ここのところ、歌の途中をカットしているが、全部うたっているシーンをみたかった)。そこでは欺瞞であれなんであれ、植民地支配の根深かさ――支配された人々の脳裏に刻まれた一つ一つの記憶は生涯消えることがないという――歴史的な重さを思い知らされる。
なお、この映画は、東京・下北沢のシネアートン下北沢で六月二四日から七月七日まで、夜八時三〇分からのレイトショーで公開される。できるだけ多くの日本人にみてほしいと願わずにおれないが、こういう場所の小劇場でしか上映されないところに、いまの日本の救いがたさが現れている。
(月刊「東京」は、東京自治問題研究所が発行している。木下昌明氏の「映画から見えてくる世界」を連載中。1部350円。TEL03-5976-2571 http://www.tokyo-jichiken.org)
Created bystaff01. Created on 2006-06-28 11:34:06 / Last modified on 2006-06-28 14:58:47 Copyright: Default