
朝鮮南部と日本の関係に迫る歴史研究
『加耶/任那―古代朝鮮に倭の拠点はあったか』(仁藤敦史 著、中公新書、本体900円+税)評者:加藤直樹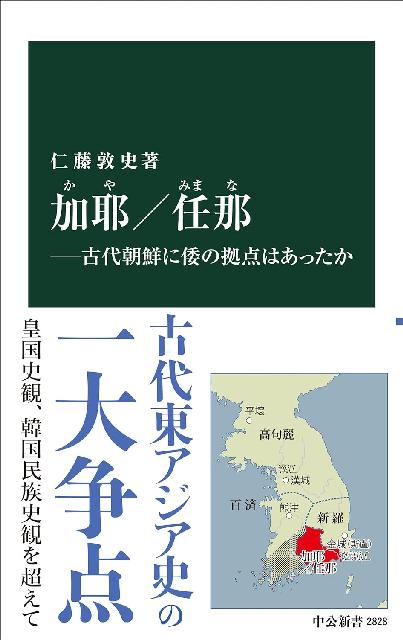
古代の日本が朝鮮を従えていたという神話の重要な部分となったのが、「任那(みまな)日本府」だ。「日本書紀」に登場するこの言葉は、戦前は、古代日本が朝鮮南部に持っていた出先機関あるいは植民地のことだと解釈されていた。
戦後、皇国史観から解放された歴史研究は、もはやそのようには考えなくない。「任那日本府」は教科書から消え、古代の朝鮮南部には伽耶諸国と呼ばれる小国群があったと記述されることが普通になった。かといって「じゃあ、任那日本府って何のことだったんだ」という疑問は、少なくとも一般人の教養のなかでは解消されないままだ。しかも近年、全羅南道で十数基の前方後円墳が発見されている。この地域が日本――ではなく倭、との深い関係をもっていたこと自体は否定できない。
任那日本府とは何だったのか。朝鮮南部と日本――倭との関係は、実際にはどのようなものだったのか。国立歴史民俗博物館教授の著者は、江戸時代からの研究の歴史を踏まえつつ、最新の考古学的な知見なども交えて、それを明快に説明している。
結論から言えば、「任那」とは、本来は伽耶諸国の中で有力な国である「金官(加羅)」のことを指し、ひいては伽耶諸国を指して使われていた言葉だ。では「任那日本府」とは何か。「府」は政府という意味ではなく、「役人」という意味だという。著者は、「任那日本府」とは、伽耶諸国の王たちに仕えた倭人系の豪族のことだと説明する。
彼らは日本の出先機関ではなかった。玄界灘を超えて移住した、主に筑紫の国から来た倭人たちであり、そのなかの豪族は、伽耶のそれぞれの王に仕えた。伽耶だけでなく、百済にも倭系豪族はいた。前方後円墳の存在は、その証左だったのだ。何のことはない。倭−日本に朝鮮半島から渡ってきた渡来人がたくさんいたように、朝鮮半島にも倭人系の「渡来人」がいたということだ。
ご存じのとおり、倭は百済と組んで高句麗や新羅と対決する路線を採っていた。「日本」となる前の「倭」は、政治的には朝鮮半島の離れ小島であり、朝鮮本土で展開される政治抗争の一部をなしていた。新羅に拮抗し得る軍事力を持つ倭は、しばしば百済や伽耶諸国の要請で派兵する。この派兵のなかで、そのまま朝鮮南部に土着する人々もあらわれたのである。
当時はまだ、近代的な意味での「国」は存在しない。倭の王権にしても、列島を領域支配していたわけではない。そうしたなかで、縁あって伽耶の地に生きることになった人たちがいた。彼らは現地の人たちと結婚し、「韓子(からのこ)」「韓腹(かんぷく)」などと呼ばれる新しい世代を生み出す。彼らは倭のためではなく、彼らが根付いた伽耶の国々のために、その独立を守るために働いたと著者は書く。吾は任那に拠(よ)り有(たも)ちて、亦(また)日本に通わじ――私は任那に定着しており、もう倭王の命令は聞かないと、ある豪族は言い放った。
だが、百済と新羅という大国に挟まれた伽耶諸国は、次第に双方から侵食されていき、最終的には新羅に飲み込まれた。倭と縁の深かった金官の王も、新羅王に服従を誓った。そのひ孫が、金春秋=武烈王のもとで新羅による朝鮮統一に貢献した武将・金庾信である。そして金官とは今の慶尚南道・金海市であり、韓国最大の本貫である金海金氏は、金官王の系譜ということになっている。
伽耶の滅亡、百済の衰退(さらに滅亡)とともに朝鮮半島の政治空間から押し出された倭は、その後、「日本」と名乗り、かつて持っていた伽耶諸国への影響力を「日本は朝鮮を服属させていた」という神話へと肥大化させ、中国と並ぶ東海の小帝国という途方もない自意識を育てていく。こうして、私たちの知る日本と朝鮮の歪んだ関係が始まった。
伽耶諸国が自らを語る史料はほとんど存在しないそうだ。ただ新羅への服属の際に演奏されたという記録が残る「伽耶琴」は、今でも韓国で演奏されている。玄界灘に面した伽耶の国々に、どんな風が吹いていたのか。今となっては分からない。倭王ではなく伽耶の独立のために闘った倭系伽耶人たちの思いも、歴史の彼方に消えてしまった。
Created by staff01. Last modified on 2025-08-15 12:16:54 Copyright: Default
