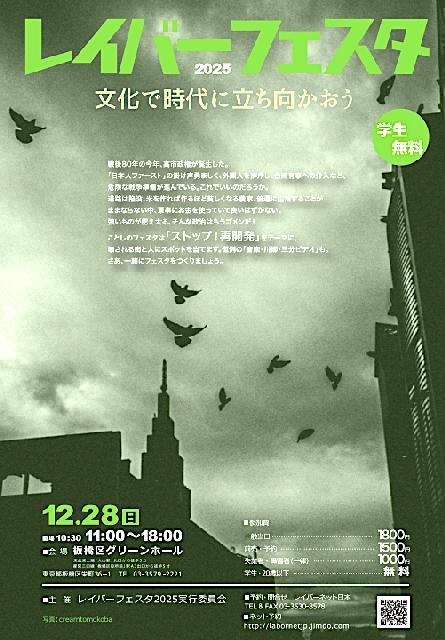今日8月22日は、115年前(1910年)に「韓国併合に関する条約」が調印され、日本が韓国を完全に植民地化した日です(写真は併合に反対して起こった1919年の3・1独立運動)。
今日8月22日は、115年前(1910年)に「韓国併合に関する条約」が調印され、日本が韓国を完全に植民地化した日です(写真は併合に反対して起こった1919年の3・1独立運動)。 そもそも武力で韓国を支配下に置いたにもかかわらず、「条約」という体裁をとり、しかも「併合」というあいまいな言葉を使ったこと自体、日本の狡猾さが表れています。
「日本国家が韓国全土を軍事占領した力により、韓国を強制的に併合したことは不義不当なことであったが、その併合を韓国皇帝が願い出たので、日本の天皇が承諾して、実行したものだという虚偽の物語を条約という文書を中心に重ねて説明したことも併合の事実以上に重大な、朝鮮民族を辱めた不義不当な行為であった」(和田春樹著『韓国併合一一〇年後の真実―条約による併合という欺瞞』岩波ブックレット2019年)
「強制的に併合した」とはどういうことか。1910年までの経過を確認しましょう。
<日露戦争(1904年2月)では、日本はロシアとの交戦以前に、朝鮮の領海深く海底電線の敷設や連合艦隊の根拠地として鎮海湾の制圧、馬山の電信局の占領など…世界に公表できないような不法行為の上に、韓国には日韓議定書を結ばせ(04年2月23日)、日露講和条約(05年9月5日)のすぐ後には、続いて第二次日韓協約、いわゆる「保護条約」(05年11月17日)を結んで外交権を奪い、そして1907年7月24日、「韓国内政の全権掌握に関する日韓協約(第三次日韓協約)および不公表覚書」によって、韓国の軍隊を解散させ、その上で「韓国併合」におよんだのです。
明治維新から43年、日本は日清戦争、義和団鎮圧戦争、そして日露戦争をへて朝鮮を完全に従属させ植民地とする目標を実現しました。>(中塚明著『これだけは知っておきたい 日本と韓国・朝鮮の歴史 増補改訂版』高文研2022年)
決定的な画期となったのは「保護条約」(乙巳<いっし>条約)ですが、軍事力を背景にこれを強行したのが、敗戦後日本が長い間「紙幣の顔」にしてきた伊藤博文でした。
「伊藤は皇帝を脅迫し、韓国の大臣一人ひとりに、賛成か、反対かを問いつめ、あくまで反対した首相や大蔵大臣らを退け…強引に調印に持ち込んだのです」(中塚氏前掲書)
「併合条約」が「韓国皇帝が願い出たので日本の天皇が承諾」した形をとった背景には、天皇制をめぐる状況がありました。
<天皇制イデオロギーの神がかった部分については…幸徳秋水なんかの批判がぼつぼつ出てきたりする中で…天皇制をさらに補強する必要が感じられた時期が、ちょうど朝鮮を植民地化した段階であり、大衆が朝鮮にいろんな形で動員されて…排外主義の側に組織されていく。…天皇制と植民地支配そして「アジア主義」が一体となって、日本人を体制のイデオロギーに組み込む役割を果たした。>(梶村秀樹著『排外主義克服のための朝鮮史』平凡社ライブラリー2014年)
天皇制と植民地主義・排外主義。この悪のスパイラル(螺旋)は、過ぎ去った過去のことと言えるでしょうか。
故・中塚明氏は前掲書でこう警鐘を鳴らしていました。
「いま私たちの国、日本では、この二つの戦争(日清・日露)がどういう戦争であったのか、日本はなにを目指してどういう戦争をしたのか、日本の侵略をうけた朝鮮では朝鮮人はどうしたのか、どんな動きがあったのか、そんなことについて、まったく知らない。戦争といえば「真珠湾から広島まで」、「アメリカと戦って負けた太平洋戦争」とは知っていても、明治の戦争などは知らない、という日本人がほとんどです」
「戦後80年」ということでメディアは太平洋戦争の歴史を「継承」する必要性を強調しています。しかし、1945年の敗戦を1894年の日清戦争からの戦争の歴史の中でとらえる視点は皆無です。
「韓国併合115年」を日清戦争からの侵略・植民地支配の歴史の中で捉え直し、教訓を「継承」していくことこそ、軍靴の響きが大きくなっている今の日本に必要なのではないでしょうか。