
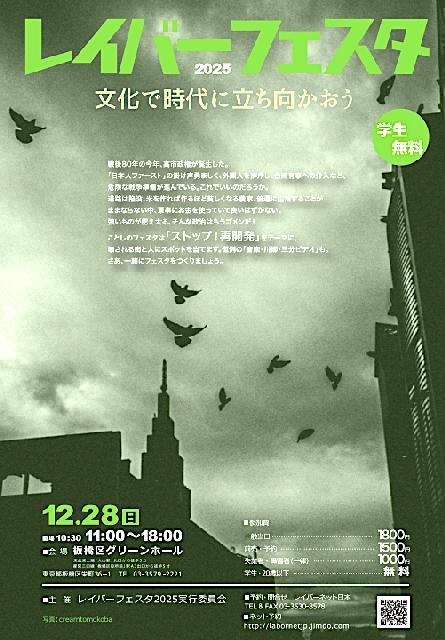
■2.0チャンネル
・映画祭報告(7/27)
・レイバーネットTV(12/10)
・あるくラジオ(11/1)
・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告
・ブッククラブ(12/13)
・シネクラブ(10/11)
・ねりまの会(6/28)
・フィールドワーク(6.1報告)
・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)
・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画
●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10)
●〔週刊 本の発見〕第416回(2025/12/25)
●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6)
●川柳「笑い茸」NO.164(2025/11/25)
●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)
●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14)
●「美術館めぐり」第18回(2025/12/22)
★カンパのお願い
■メディア系サイト
原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP
|
|
|
ログイン |
|
情報提供 |
|
|
|
Status: published View |
傍若無人の全北バス会社、市議会の仲裁にも動じず
「民主労総は暴力集団、対話はできない」
バスストライキの社会的合意のための市民討論会が2月23日、全州市議会主催で 開かれたが、使用者側の相変わらずの傍若無人な態度で大きなため息だけを残 して終わった。
今回の討論会は、市内バスのストライキが長期化しており、市民の不便と不満 が高まっているが、労使間の対話も中断し、事態解決の見通しが暗い状態で、 社会的合意を通じた解決方案を模索するために開かれた。

全北大のキム・ウィス教授が討論会の進行を引き受け、『全州市バス正常化の ための提言』を主題にアン・ホヨン弁護士が問題提起し、使用者側からは全北 バス事業組合が、労働側からは民主労総全北本部が、各々の立場を陳述した。 討論者には参与自治全北市民連帯と全北対立調停委員会、全州市建設交通局長 が出た。
アン・ホヨン弁護士は「労組がすぐストライキを解除できる代案として、事業 主が労組に暫定的な交渉当事者としての地位と誠実交渉を約束し、事業主には 労組の交渉当事者の地位は暫定的な地位であり、今後、法院で交渉当事者の地 位がないと確定すれば現合意の効力とこれによる交渉の結果を否定できるよう に道を開こう」と提案した。
しかし使用者側は、労働部がバスストライキを22日、再度不法ストライキだと 規定し、代替人材の投入は合法だと解釈したことに力を得て、不法ストライキ だと主張し続け、一部の暴力行為を強調して民主労総は暴力集団だと言って、 彼らとは交渉できないという態度を続けた。
また市長、道知事をはじめとする地方自治体と市民団体が保証人になるという 社会的合意案にも、「交渉は第三者が介入するのではなく、労使がすること」 と拒否した。ただし、「複数労組が施行される7月になれば、その時に窓口の 単一化をすれば交渉できる」と話した。
市庁も直接の当事者ではないが、市民の不便を最小にするために、代替バスを 投入するなどで最善を尽くしているという立場だけを繰り返した。
対立調停委員会のチェ・ドゥヒョン事務局長は、「不法行為と交渉権を分離し なければならない」と主張し、参与自治全北市民連帯キム・ナムギュ事務局長 は「使用者側が7月1日まで訴訟を続け、労組を無力化する意図のようだ。法的 な判断については市民訴訟により、どちらも責任を問う」と話した。
民主労総のイ・チャンソク事務局長は「民主労総はすでにすべてに譲歩した。 団体協約も新しく採決せず、韓国労総の団体協約を守るといった。交渉のため の対話もできると話した。しかし使用者側はすべて引っくり返した」と話した。 使用者側は、これについてのきちんと回答をすることができず、最後まで主張 を崩さなかった。
2時間以上討論会が続いたが、合意点は全く探せず、討論会に参加したある市民 は「とても絶望的な気分だ。市民の立場でこの討論会を見て、誰もまともだと は言わない」とし「誰もが安易無事主義だ。次の選挙の時は覚えてろと言いた い」と残念さを吐露した。
キム教授は討論をまとめて「討論会の記事が出ると、市民のため息と怒りにつ ながるのではないかと思う。片方は論理、一貫性、受け入れ態度が全くできて いない。今回のストライキについて市長と道知事の無能を示す」と話した。
一方、バス会社は運行率を上げるために新規人材を採用しているという。だが 労働側は、これは厳然たる不法という立場だ。全北本部のパク・チェスン組織 局長は、「労働部が行政指針でしかないマニュアルで、不法ストライキだとい うが、続々と出ている法院の判例を見るだけでもバスストライキは合法であり、 代替人材の投入は明らかな不法だ」とし「代替人材が投入されないように必ず 防ぐ」と明らかにした。(記事提携=チャムソリ)
翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可( 仮訳 )に従います。
Created byStaff. Created on 2011-02-25 10:48:18 / Last modified on 2011-02-25 10:48:19 Copyright: Default
世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ
