
・レイバーフェスタ2025
・レイバーネットTV(12/10)
・あるくラジオ(11/1)
・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告
・ブッククラブ(12/13)
・シネクラブ(10/11)
・ねりまの会(6/28)
・フィールドワーク(6.1報告)
・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)
・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画
●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10)
●〔週刊 本の発見〕第416回(2025/12/25)
●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6)
●川柳「笑い茸」NO.164(2025/11/25)
●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)
●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14)
●「美術館めぐり」第18回(2025/12/22)
★カンパのお願い
■メディア系サイト
原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP
|
|
|
ログイン |
|
情報提供 |
|
|
|
Status: published View |

ユリと「僕」を見つめる詩集
『小さなユリと』(黒田三郎・夏葉社)評者:那須研一
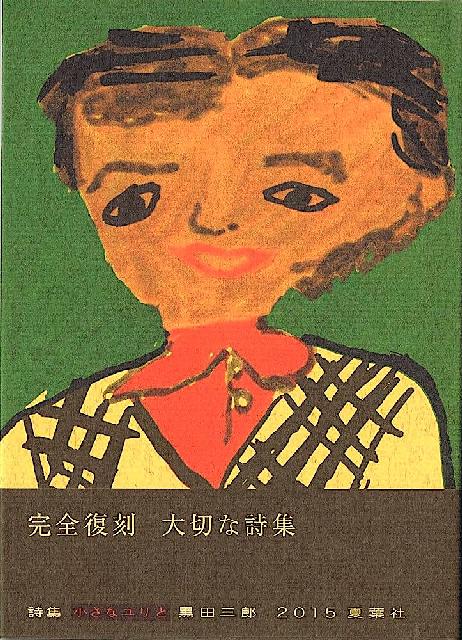
「なっすー!家に帰ったら玄関にスズメバチがいて入れなかった!」
「なっすー!今日、給食の時マナちゃんが頭から牛乳かぶった!」
「なっすー!アオちゃんが朝顔のところで転んだ!」
来所するなり、複数名が同時になっすー(私)に訴える。スズメバチの大きさもマナちゃんの奇行の理由も気になるけど、アオちゃん大丈夫!?
また別の子が「なっすー!段ボール出して!」
「なっすーはショウトクタイシではありません!一人ずつ話してください!」
「ショウジキオウジって誰?」
…黒田さんも奮闘しています。
「夕方の三十分」黒田三郎
コンロから御飯をおろす
卵を割ってかきまぜる
合間にウィスキイをひと口飲む
折紙で赤い鶴を折る
ネギを切る
一畳に足りない台所につっ立ったままで
夕方の三十分
僕は腕のいい女中で
酒飲みで
オトーチャマ
小さなユリの御機嫌とりまで
いっぺんにやらなきゃならん
半日他人の家で暮したので
小さなユリはいっぺんにいろんなことを言う
「ホンヨンデェ オトーチャマ」
「コノヒモホドイテェ オトーチャマ」
「ココハサミデキッテェ オトーチャマ」
卵焼をかえそうと
一心不乱のところに
あわててユリが駈けこんでくる
「オシッコデルノー オトーチャマ」
だんだん僕は不機嫌になってくる
(後略)
ユリちゃんは「半日他人の家で暮らしたので」オトーチャマに話がしたくてしょうがない。でも、夕飯作りに大わらわの父が可愛い娘に対して「だんだん不機嫌になる」のも無理はない。「僕」とユリちゃんの一挙手一投足と表情が目に見えるよう。
黒田三郎氏。1919年生まれ。戦後詩の画期となる詩誌『荒地』創刊に参加。『歴程』同人、『詩人会議』議長としても活動。NHKの局員でもあった。
「9月の風」
ユリはかかさずピアノに行っている?
夜は八時半にちゃんとねてる?
ねる前歯はみがいてるの?
日曜の午後の病院の面会室で
僕の顔を見るなり
それが妻のあいさつ
入院中のオカーチャマは娘のことが気がかり。夫のことも心配。ユリに質問する。
オトーチャマいつもお酒飲む?
沢山飲む?ウン 飲むけど
小さなユリがちらりと僕の顔を見る
少しよ
今のユリちゃんにとってオトーチャマはニ人暮らしの同志。「少しよ」に万感が籠もる。
「顔の中のひとつ」
始発の通勤電車を待ってフォームに行列をつくっているひとびと
その行列のなかにまぎれこんで
僕はほっとひと息つく
行列のなかにまぎれこんでしまえば
僕も普通の通勤者のひとり
僕が遅れて勤めにゆくことに気のつく者は誰もいない
たった今小さなユリを幼稚園へ送って来たと知る者は誰もいない
顔であることになれきった顔の群れに入り
僕もまたその顔のひとつになる
(中略)
坐りおくれて
僕は戸口に立ち
しずかに外を見る
見なれた風景
(中略)
外を見ることで
僕もよそよきの顔をとりかえす
娘を幼稚園に送って来た「僕」は、満員電車で窓外の「見なれた風景」に目をやることで「小さなユリのオトーチャマ」から「よそゆきの顔」の「普通の通勤者のひとり」になる。勤め先の最寄り駅で下車したら「僕」は私であることを閑却したまま今日の仕事をするのだろう。
でもやはり、詩人は自分の心から目を背けたまままではいられない。「いてはならないところにいるような こころのやましさ」(「夕焼け」)から逃れられない。「ぐずで能なしの月給取り奴!」(「月給取り奴」)と自嘲せずにはいられない。飲まずにはいられない。
「洗濯」
酒を飲み
ユリを泣かせ
うじうじといじけて
会社を休み
いいところはひとつもないのだ
意気地なし
恥知らず
ろくでなしの飲んだくれ
でも、詩人を世界につなぎとめるのは「小さなユリ」。会社をサボって自虐する詩人はやるべきことを思い立つ。
(中略)
洗い場へ駆けてゆく
小さなユリのシュミーズを洗い
パンツを洗い
誰もいないアパートの洗い場で
見えない敵にひとりいどむ
自分であるための闘い。しかし、糧を得るための些事からは逃れようがない。救いとなるのはやはり「小さなユリ」。娘の手を引いて幼稚園に送るひととき。
「小さなあまりにも小さな」
(前略)
自己嫌悪と無力感を
さりげなく微笑でつつみ
けさも小さなユリの手を引いて
冬も間近い木洩れ日の道
その道のうえを
初夏には紋白蝶がとんでいたっけ
「オトーチャマ イヌよ」
「あの犬可愛いね」
歩いているうちに
歩いていることだけが僕のすべてになる
小さなユリと手をつないで
ユリ、そして彼女と手をつないでいる自分を見つめることで「僕」は「ぐずで能なしの月給取り」でも「ろくでなしの飲んだくれ」でもなくなる。「歩いていることだけが僕のすべてになる」。
【『小さなユリと』は1960年に昭森社から発刊された詩集。長らく入手困難になっていたのを、2015年に夏葉社が復刻、今年10月に重版。上掲の表紙絵は小さなユリちゃんの作品。オトーチャマへの思慕が溢れる。】
Created by staff01. Last modified on 2025-11-20 10:09:10 Copyright: Default


