第13話 抗争に明け暮れる‥‥の巻 新戸育郎 (2008年6月8日掲載・連載の一覧はこちらへ。毎週日曜日更新)
安い時給を我慢して勤める旭日教育研究所。だからこそせめて労働環境は心地よいものであってほしい。ところがこの塾のおばさん先生とは対立が深まるばかり。おまけに、冗談で言った生徒への「脅し」が大騒ぎに発展してしまった。
《これでいいの? 英語テキスト》
この塾で使っている英語のテキストというのが、NHKの「基礎英語」であることは前に言った。
そのときは教え方のいい加減さを説明したが、それ以前に、このテキスト自体のでたらめぶりも言っておかなくてはならない。
数の数え方を教えている個所だ。文房具の絵が描いてある。1本の鉛筆、1冊の本。それから2本の鉛筆、2冊の本、等々。もちろん a book, two books と言わせたいわけだ。
問題はその次、はさみの絵がある。しかもそれは2個のはさみになっている。1個のはさみではないのだ。何といういんちきなのだろう。はさみは1個でも複数形になるからこそ、そこに日本語と英語との発想の違い、文化の違いが際だってくるのじゃないか。
しかし「基礎英語」ではそれを隠してしまっている。おそらく a pair of などの表現を教えなければならない面倒さを避けているのだろうが、こういう形で教わった子供たちは必ずあとで混乱するにちがいない。1つのはさみでも two scissors と言うかもしれないし、 a scissor と思うかもしれない。1個、2個の概念が英語と日本語とでは違うのだということを子どもたちに発見させないで、何が「複数形」の学習だろうか。
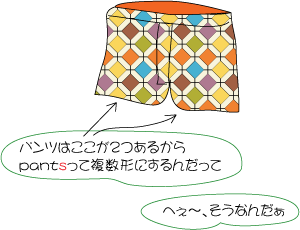
で、話を旭日教育研究所に戻す。
《すさまじい書類管理》
矢中おばさんから、書類をどういう風に整理すれば効率がよいか考えてほしいと言われ、この塾の書類の整理状況を調べてみた。
唖然としたのは、その分類のでたらめさ。
ここには膨大な種類のテストプリントがある。ふつう、学年別に分ける、科目別に並べる、新項目と旧項目を区別する‥‥など整理して行くだろう。ところがそれがごちゃまぜだ。中1の英語が「中1−23」というファイルに入っていたとすると、中2は「C2−161」となっていたりする。abc順に並んでいるファイルをたどっていくと、突如いろは順に変わっている。同じ書類が別の分類のファイルに入っている‥‥。
もうお話にならないでたらめぶりで、これは大変だと思いながら「書類はこのように分類して」と提案すると、矢中おばさんはシラッとして「慣れればわかりますから」。
整理の方法を考えてほしいと言ったのはそっちじゃないのかぁ、と怒鳴りたいのを我慢して、じゃ好きなようにやるがいいさと思うしかない。我流でやってきたことのツケがこの混乱に現れているのだが、ご本人は万人に使いやすいシステムを考える気などない。情報は共有化できないと意味がないということに理解が及ばないらしい。
さらにまた別の時、進度の記録をどうすればよいかと尋ねられたので、日誌に書き込みできる欄を大きくとってもらえればやりやすくなるといったら、それではどうの、そんなことを書く欄ではない、いちいち遡って見るのは大変、等々、否定の言葉しか返って来ない。
要は自分がやっていること以外はやりたくないわけで、それなら「新戸先生教えてください」などと偽善ぶって相談をもちかけたりしなければいいのにと思う。
一事が万事この調子で、この固い頭は削岩機でも壊せそうにない。
新中学1年生の女の子3人組、例のカシマシ娘までが、「おばさん先生、きらいだよねぇ‥‥」などと言っているのを聞いて、ごもっともと思ってしまう。
ときどき手伝いにくるバイトの女子大生と雑談をしていたとき、彼女がふと、問わず語りに言った。「前の先生が辞めたのは、谷中先生と喧嘩しちゃったからなんですよねぇ」。
そういうことなんだなぁ。誰もがあのおばさんとうまくいかない。しかし本人は自分が原因だなんて思ってもいないんだろうなぁ。好々爺の塾長がいるから何とかもっているが、何しろ高齢の塾長、もし亡くなったらこの塾は一体どうなるんだろう。
《コワイ先生出現》
そしてそのカシマシ娘。実に騒がしく落ち着きがないこの3人にはかなり手を焼いた。なにしろ話す言葉と言えば、うざい〜、ちょームカツクぅ、だ。
あまりに言うことを聞かないあるとき、
「こんな調子じゃ、痛い目を見るぞ」
「え〜、なに〜?」
「あのな、ぼくは前の塾で生徒を殴ってクビになっちゃったんだよ」
「え〜っ、先生ってコワイ先生なのぉ?」
「そうだよ。おとなしく言うことを聞かないと、どんな目に遭うか知らないぞ〜」
「え〜ぇ‥‥」
ちょっとだけおとなしくなったカシマシ娘を見てにやっと笑った。
ところがその2、3日後だったろうか、あの温和な塾長が血相変えて私に詰め寄って来たのだ。
「新戸先生、前の塾で生徒を殴って辞めたというのは本当ですか!」
こちらも面食らった。まさかカシマシ娘に言った冗談が、そのまま塾長に伝わるとは思ってもいなかった。
「仮に冗談だとしても、親に知れると大変なことになるんですよ。新戸先生は今後塾を経営されるつもりかもしれない。それだったらなおさら、言っていいことと悪いことを判断していただかないと‥‥」
懇々と説教されてしまった。
中学1年生、それもついこの間まで小学生だった子どもに、冗談が通じると思ったのが間違いだった。高校生を教えるのとはわけが違う、とこのときは痛切に思った。
このあと、もう1件、塾長からのクレームがあった。
これは事実無根のひどい話だったが、テストプリントの答えをある生徒に教えただろう、というものだった。なぜかというと、普段成績の悪いその子が、そのテストに限って成績がよいからだと。
そんなことをしたところで、私に何のメリットもない。何を好き好んでそんな面倒なことをやらなければならないか。
私への濡れ衣もひどいものだが、その子もえらく見くびられたものだと思う。たまによい成績をとることぐらい誰にでもあるはずではないか。
なぜ私がやったという話になったのかはよくわからない。恐らくそれ以前に、矢中おばさんがさんざん私の悪口を塾長に吹き込んでいたからではないかと思う。
みんなから嫌われているおばさん先生に信用されなくても全然平気だが、このとき塾長から露骨に疑いの目で見られたのには正直参った。同時に、もう潮時だと思った。塾長に信頼されないのなら、やって行けるわけもない。
話をするうちにようやく疑いは晴れたようだったが、この塾でこれ以上長くいても意味はないとその時思った。
《さらば旭日教育研究所》
何日かあと、辞める意向を塾長に伝えた。
穏やかな話し合いの結果、ともかく月内までは仕事をしてくださいということになり、しばらくは継続することになった。
最後の日、生徒たちに辞めることを伝える。あっさりしているが一応さようならを言ってくれた。塾には何の未練もないが、子供たちにはやはり多少の情が移っていることを感じる。
塾長は「こんな形で残念だが」と言ってくれた。矢中おばさんにもとりあえず型通りの挨拶をする。ま、なんとか不快な別れ方だけはせずに済んだ。
結局、わずか4ヶ月足らずで、極安時給のお仕事は終わった。このあとまた、旭日教育研究所では新講師の募集なのだろう。「前の先生はおばさん先生と喧嘩して辞めた」てなうわさが広まるのだろうか‥‥。
Created bystaff01. Created on 2008-06-08 16:00:58 / Last modified on 2008-06-08 16:04:56 Copyright: Default
