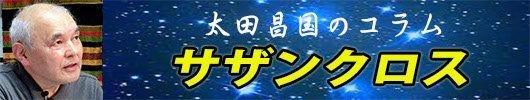●第101回 2025年5月10日(毎月10日)
日韓条約反対闘争60周年の年に
 今年に入って2回ほど、60年前の1965年、私が学生時代に関わった活動に関して、苦い記憶を人前で話さなければならない機会があった。日韓条約締結反対闘争を回顧して、である。*写真=日韓条約調印式
今年に入って2回ほど、60年前の1965年、私が学生時代に関わった活動に関して、苦い記憶を人前で話さなければならない機会があった。日韓条約締結反対闘争を回顧して、である。*写真=日韓条約調印式
日本帝国の敗戦から6年後の1951年9月、第二次世界大戦の戦勝国側である連合国側と、敗戦国である日本との講和条約が調印された。翌年52年4月、この条約は発効した。連合国と日本の戦争状態は終結した。だが、日本の植民地支配から解放された朝鮮半島は、その3年後に南北に分断され、50年6月には朝鮮戦争が勃発していた。その戦火が止まぬさなかでの対日講和条約の発効であった。連合国の主軸たる米国は戦勝国の有利な立場を十分に活用し、講話条約と同時に日本との間に安全保障条約を締結した。米国からすれば、軍事同盟国となった日本は、講和条約を結んだ以上は東アジアにおいて共に「反共の砦」であるべき韓国および中華民国との国交正常化交渉を急がねばならぬと考えて、あと押ししたのだろう。蒋介石率いる中華民国政府とはすぐ交渉がまとまった。日韓の交渉も、講和条約締結を見越して、1951年10月には第一次会談・予備会談が始まっていた。
だが、交渉は難航した。その最大の理由は、日本側が旧植民地=朝鮮にある日本人の財産に対する対韓請求権を主張したからである。対日講和条約には、日本が、旧植民地において米軍政府によって行なわれた財産処理の効力を承認するとの項目があるのだが、この点に関して日本側は植民地支配の「正当性」をめぐる論議を後景に押しやり、ハーグ陸戦法規(1899年)が定めた私有財産没収禁止条項を盾にしたのだった。

だが、この同じ年、交渉は急速に進展した。植民地支配責任があることを明言しない日本に対する韓国民衆の怒りを背景に、米韓両政府は日本が「謝罪特使」を韓国に派遣するよう提案した。日本側は65年2月これを受け入れるとともに、韓国民衆の対日感情を和らげるために、国交正常化を待たずに2000万ドルの対韓緊急援助を行なうことにした。加えて米国がベトナム戦争に介入する可能性が高まるとともに、米韓は米軍支援のために韓国軍をベトナムに派遣する検討を始めた。その立場からすれば「日米韓」の一体化は不可欠であり、日韓国交正常化はその要をなすものだった。日米韓三国政府のそれぞれの思惑が絡み合っての「妥協」が図られた。
1964年12月の第7次会談以降、植民地支配をいかに捉えるかという基本問題については、日韓双方が如何ようにも解釈できる文言で妥協した。かくして65年6月には、日韓基本条約および請求権、漁業、法的地位の三協定の調印が成った。韓国の民衆は、自国政府の譲歩を糾弾し、「植民地支配を合法化」する条約だとして批判した。他方、日本の野党・労働運動・学生運動による条約批判の論点は、南北分断の固定化・日米韓軍事同盟の強化・日本独占資本の韓国侵略などに集約されていた。私自身が関わっていた小さな学生グループの観点もそれを越えるものではなかった。日本による朝鮮の植民地支配をいかに総括して、両国支配層が締結しようとしている条約のあり方を批判するか――この問題意識を私自身がまったく欠いていた。
同時代に、眼前で展開されているベトナム民衆の戦い――強大な北アメリカ帝国主義の軍隊の侵略に対する果敢な戦いを見て、私(たち)が民族・植民地問題の重要性に覚醒するのは、日韓闘争の年=1965年の後半である。朴慶植の『朝鮮人強制連行の記録』のような衝撃的な証言記録も刊行されて(未來社、1965年5月)、それにもあと押しされた。この事実に遅ればせながら気づいて、私はひどく恥ずかしい気持ちがした。そこでは、当然にも、個々人の歴史的感度が問われていた。同時に、社会総体の問題としては、1945年の敗戦の在り方、戦争責任問題の放置、新たに制定された憲法9条に守られての「戦後民主主義と平和」の謳歌(同時期のアジア周辺地域では、日本帝国の過去の植民地支配と侵略戦争にも少なくない責任がある内戦・軍事独裁・極度の貧困状況が続いていた)――など、1945年→1965年を貫く「戦後20年」の内実が問われていたのだ。
私より14歳年上のフランス文学者・故鈴木道彦は、1965年11月に開かれたシンポジウム「日韓問題と日本の知識人」において自らが行なった発言について次のように回顧している。「(私は)戦前の植民地帝国の生んだ状況を放置してきた『戦後責任』こそ真っ先に問われなければならず、政府自民党はもとよりだが、『革新勢力』と言われた野党側にもこの認識がまるで不足していたことを指摘した。若輩者の生意気な意見で、顧みると冷や汗が出るが、その背景には、当時ずっと考え続けていた小松川事件と『民族責任』の問題が横たわっていた」(鈴木道彦『越境の時 一九六〇年代と在日』(集英社新書、2007年)。
鈴木が36歳の時の発言で、およそ40年後にこれを回顧した時に「若輩者の生意気な意見で、顧みると冷や汗が出る」と書いた心境がよく理解できない。もっとこのような意見が、あの時代の渦中で出なければならなかった。
このようなことが胸に突き刺さってくるから、1965年日韓闘争を回顧することは苦い作業なのだ。
Created by staff01. Last modified on 2025-05-13 13:42:25 Copyright: Default