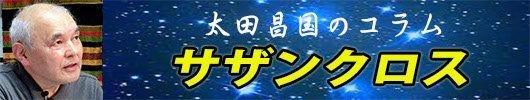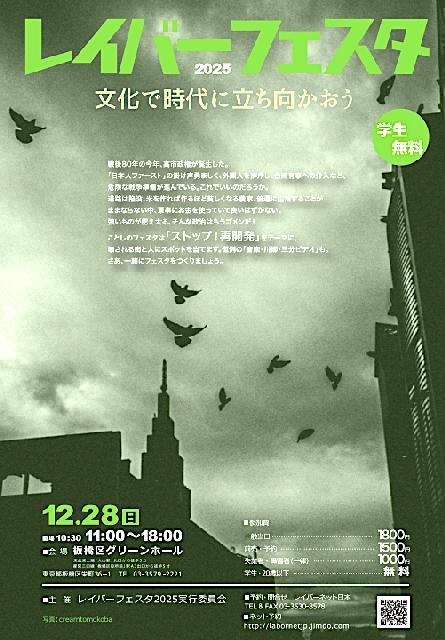
■サブチャンネル
・映画祭報告(7/27)
・レイバーネットTV(12/10)
・あるくラジオ(11/1)
・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告
・ブッククラブ(12/13)
・シネクラブ(10/11)
・ねりまの会(6/28)
・フィールドワーク(6.1報告)
・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)
・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画
●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10)
●〔週刊 本の発見〕第415回(2025/12/18)
●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6)
●川柳「笑い茸」NO.164(2025/11/25)
●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)
●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14)
●「美術館めぐり」第18回(2025/12/22)
★カンパのお願い
■メディア系サイト
原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP
|
|
|
ログイン |
|
情報提供 |
|
|
|
Status: published View |
●第97回 2024年12月10日(毎月10日)
植民地主義の巻き返しのなかで続く略奪文化財の返還
「中国文化財返還運動を進める会」(以下、「進める会」と略)からの依頼で、先日「脱植民地主義と文化財返還の意味」という講演を行なった。https://cbunkazaihenkan.com/2024/11/14/
「進める会」の存在を知って、私はすぐ賛助会員になったが、数ヶ月に一度の頻度でニュースレターが送られてくる。すでに『中国文化財の返還―私たちの責務』『世界史のなかの文化財返還―未決の植民地主義を超えるために』『〈帝国大学〉の学知を問う』と題する3冊のブックレットも刊行されている。それを読むと、まず返還運動の対象とする目標を、靖国神社大鳥居の手前にある一対の獅子像(写真)、栃木県矢板市の山縣有朋記念館に置かれた一体の獅子像、皇居内で非公開のまま保管されている巨大な石碑「鴻臚井の碑」の3点に定めたことがわかる。前者2件の獅子像は、日本軍が日清戦争の際に遼寧省海城市の三学寺から奪い、後者は日露戦争の際に遼寧省旅順市の黄金山麓から奪ったもので、日本軍の記録では「戦利品」と記載されているという(一瀬敬一郎「中国文化財返還運動から日中友好を実現しよう」。上記『中国文化財の返還―私たちの責務』所収)。
日本の戦争史をふりかえる時、従来は「15年戦争」【1931年の、関東軍による柳条湖の満鉄線路爆破(いわゆる満洲事変)から、敗戦の1945年までを指す】という呼称がよく使われてきた。あえて元号を使えば、それは日本が関わった戦争の発端と終末を、「昭和」前期に限定して据える歴史観だ。私は、戦争国家としての近代日本の成り立ちを思えば、「明治」維新以降に次第に確立されて、「大正」および「昭和前期」を貫いた長い射程を捉えて、「50年戦争」と呼ぶのがよいとこの間考えてきた(同じ考えのひとは、他にもおられる)。発端は1894年の日清戦争で、終末は敗戦の1945年である。だから、「進める会」が、日清戦争時の「戦利品」の返還を優先的に取り上げていることに、私は共感を覚える。また、「進める会」は、靖国神社、山縣有朋記念館、宮内庁など、他国の文化財を占有している施設の責任者と面談したり、質問状を送ったりもしている。今年に入って、対象はさらに、東大総合博物館や東大東洋文研究所が所蔵している収奪文化財にも及んでいる。中国側で文化財の回収に当たっている当事者・機関との連携もできており、これらの努力が今後どのようにして具体的な成果を挙げるかに注目し、連帯したいものだと思う。
今回の講演を準備しながら考えたことを、簡潔に要約しておきたい。
脱植民地主義の文脈で、過ぎ去りつつある21世紀初頭の4半世紀を顧みるなら、植民地主義を継続させようとする側の巻き返しが目立つ。2001年から2021年まで米国を主軸に展開された20年間の「対テロ戦争」の犠牲者数が、戦闘による直接的な犠牲者=92万9000人、戦争による経済の破綻、医療インフラの崩壊、環境汚染、住民のトラウマや暴力など間接的な死者=360万〜370万人で、合計450万〜460万人と推定されているにも拘らず、その重大性が世界から無視されていること。死者はイラク、アフガニスタン、パキスタン、シリア、イエメンなどの人びとであり欧米人ではないから、固有の名を持つ人間としては認識されず、黙殺されるのである。これこそ、継続する植民地主義の具体例に他ならない。この「対テロ戦争」が終わりを告げてまもない2022年、ロシア軍のウクライナ侵攻が開始された。前年のプーチン論文「ロシア人とウクライナ人の歴史的一体性について」を読めば、プーチンは大ロシア主義の立場から、ウクライナに対している事実が浮かび上がる。さらに2023年10月から今日まで続く、イスラエルがパレスチナ人を「人間の顔をした獣」と呼んで展開しているジェノサイド攻撃を見れば、それは紛れもなく、相手を対等の人間として見做さない植民地主義者特有の価値観に根ざした一方的な虐殺攻撃であることがわかる。21世紀初頭の4半世紀は、こうして、世界の2つの超大国と、中東における1つの地域大国が、植民地主義が歴史上初めて登場した15世紀末から16世紀初頭、スペイン人が現在のアメリカ大陸で繰り広げた「征服」の所業さながらに、あらゆる形態の暴力を駆使して無辜の民を殺している図がはっきりと見えてくるのである。
だが、同時に見ておかなければならない。前世紀の20世紀末をふり返るなら、以下の史実に気づく。
1990年 南アフリカ共和国で、アパルトヘイト(人種隔離)体制廃絶運動の指導者で、長期にわたって投獄されていたネルソン・マンデラが釈放される。
1991年 南アフリカ共和国で、アパルトヘイト体制廃絶。
1992年 コロンブスの大航海と「地理上の発見」から500周年(1492→1992)。ヨーロッパによる異世界植民地化の決定的な契機となったこの事態を、いかに捉えるか、という共通の問題意識に支えられた集会・デモ・シンポジウムが、世界各地で同時多発的に、実施される。当該の地・ラテンアメリカでは、「先住民族・黒人・民衆の抵抗の500年キャンペーン大陸会議」をニカラグアで開催。東京でも「500年後のコロンブス裁判」が2日間にわたって開催。
1993年 「補償に関するパン・アフリカ会議」、ナイジェリアのアブジャで開催――
「奴隷化、植民地化、新植民地化によってもたらされた損害は過去のものではなく現在のものであり、その損害はハーレムからハラレまで、ギニアからガイアナまで、ソマリアからスリナムまで及ぶ」。「重要なのは、経済的発展を奴隷労働や植民地主義に負い、父祖がアフリカ人の売買や所有、植民地化に参画していた国々の責任であり、その罪ではない」。
1993年〜2003年 国連、「先住民族の10年」を設定。
1994年 メキシコ南東部の先住民族組織・サパティスタ民族解放軍(EZLN)が、500年間に及ぶ植民地支配とその現代的形態たる新自由主義(ネオリベラリズム)の世界支配に抗議して武装蜂起。30年後の今も、自主管轄区域を堅持。
南アフリカ共和国で、4年前まで、反体制武装組織の指導者だったが故に獄中にあったネルソン・マンデラが大統領に選出。
2001年8月31日〜9月8日 国連主催「人種主義、人種差別、排外主義、および関連する不寛容に反対する世界会議」が、アパルトヘイトが廃絶された南アフリカのダーバンで開催。加害国と被害国の双方が初めて一堂に会して、討議。イスラエルによるパレスチナに対する侵略と差別をめぐる激しい討論を経て、米国とイスラエルが会議をボイコット。
2007年 国連総会で「先住民族権利宣言」採択。「第11条2,国家は、(先住民族の)彼/女らの自由で事前の情報に基づく合意なしに、また彼/女らの法律、伝統および慣習に違反して奪取された彼/女らの文化的、知的、宗教的および霊的(スピリチュアル)な財産に関して、先住民族と連携して策定された効果的な仕組みを通じた、原状回復を含む救済を与える」。「第12条1 先住民族は、彼/女らの精神的および宗教的伝統、慣習、そして儀式を表現し、実践し、発展させ、教育する権利を有し、彼/女らの宗教的及び文化的な遺跡を維持し、保護し、そして私的にそこに立ち入る権利を有し、儀式用具を使用し管理する権利を有し、遺骸/遺骨の返還に対する権利を有する。同2 国家は、関係する先住民族と連携して公平で透明性のある効果的措置を通じて、儀式用具と遺骸/遺骨のアクセスおよび/または返還を可能にするよう努める」。
* * * *
脱植民地主義に向けての、このような営々たる努力の積み重ねを、主として政府レベルにおいてではなく、非政府組織、民間団体と個人が繰り広げてきた。その蓄積された力を背景にして、文化財の返還が21世紀に入ってから徐々に実現されてきていることも知ることができる。それは、本稿冒頭で見た植民地主義の巻き返しが目立つ21世紀初頭という同時代に進行している、この世紀の別な貌なのだ。
第二次世界大戦で勝利した「連合国」側が、その名称のままに創設した「連合国」(いわゆる「国連」)の、創設時の加盟国は51カ国だった。現在では193カ国になっている。歴史上、欧米日の列強に植民地支配を受けていた第3世界(今に言う「グローバル・サウス」)の国々が増えた結果なのだが、国連総会における一国一票の原則からすれば、それらの諸国が発揮しうる力は大きい。脱植民地主義の動きも、それを背景に持つ略奪文化財返還の動き(欧米日からグローバル・サウスの国々へ)も、国際政治の在り方の大きな変化に支えられている部分がある。
植民地主義を継続させようとする勢力との攻防はなお続くだろうが、深く進行中のこの変化を見失うことがないようにしたい。
追記:中国文化財返還運動を進める会の連絡先は以下の通りである。
http://cbunkazaihenkan.com/
〒105―0003東京都港区西新橋1−21−5 一瀬法律事務所
Tel.03-3501- 5558 Mail : info@ichinoselaw.com
Created by staff01. Last modified on 2024-12-13 22:42:21 Copyright: Default