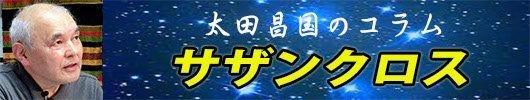●第50回 2020年12月11日(毎月10日)
免田さんの死を受けて、「死刑」の状況について
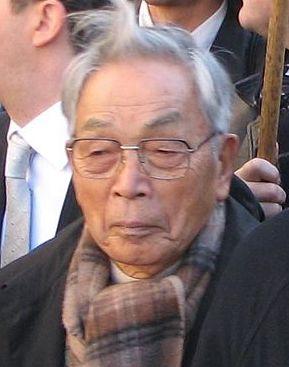
世界的にも、人権意識の高まりのなかで、1989年には国連総会で死刑廃止条約が採択され、91年に発効した。この趨勢のなかで、死刑制度廃止国も急速に増えた。だが、日本では逆流が起こった。「世論」には、死刑を含めた厳罰主義が犯罪を減少させるという、根拠のない(むしろ、現実とは真逆の)思い込みがある。メディアは、犯罪を社会全体の問題として捉える視点を欠き、「凶悪な犯人」像を作り上げるための悪煽動に明け暮れる。司法界は、冤罪や誤捜査、誤審が決して少ないないことへの反省もなく、自浄努力を欠く。政治家は、時期的に軌を一にした政党再編の渦中にあって、とりわけ自民党には持つべき理念もない世襲議員が増大した。警察官僚出身の議員であれば冤罪事件を思い出して死刑反対の立場に立ち、宗教的信念から死刑廃止を唱える自民党議員もいた時代は終わり、大方の議員からは、「票」に繋がらない死刑制度への関心は失せた。野党には、この状況に介入し、事態を転換させてゆく力がない状態が続いている。
かくして、7年8ヵ月の長きにわたった安倍政権下では39人もの死刑囚が処刑された。上川陽子氏は新政権で法相に復帰したが、前回の任期中には16人もの死刑囚の執行命令書に署名した。
このような状況に風穴を開けるために、2005年には死刑囚表現展が、2011年には死刑映画週間が始まった。私はそのいずれにも関わってきた。今年10月末の3日間、都内で開催した死刑囚表現展には2000人近い来場者があった。コロナが「小康」状態の時期であったとはいえ、狭い会場は常に「密」だった。20代、30代の若者が多く、相対的には女性の姿が目立った。アンケートに寄せられた意見から見ると、多くの人びとが製作者との対話を試み、行なわれた犯罪を社会的な文脈のなかに返す作業を行なっているように思える。そこに流れていたのは、死刑をめぐって、支配的な「世論」ともメディアとも司法界とも政治の世界とも異なる空気だった。

このレイバーネットのウェブ上に「木下昌明の映画の部屋」というコラム欄で映画評を書き綴ってこられた木下昌明さん(写真右)が亡くなられた。私は、単行本にまとめられた幾冊もの木下さんの映画評をずっと読んできていた。2017年の第7回死刑映画週間にはゲストとして来ていただいた。ヴァンサン・ペレーズ監督『ヒトラーへの285枚の葉書』(2016年)上映後、30分間ほどのお話しをしてもらった。ナチス支配下、息子の戦死を契機に父親がひとりで始めた反ナチスの活動から――妻は当初それに反対していたが、やがてふたりは協働するようになる――「一人でも行動する」ことの意味を取り出すお話だった。折から政府・自民党が企図していた共謀罪制定の動きを背景に置くと、遠い国の、過去の話に終わるものではないことが実感された。またお招きしようという思いは叶わなくなった。
*免田さんの写真=2007年、パリの第3回死刑廃止世界会議に参加した時のもの
*木下さんの写真=12.11告別式の遺影
Created by staff01. Last modified on 2020-12-11 14:42:50 Copyright: Default