●山口正紀の「言いたいことは山ほどある」(2020/5/30 不定期コラム)

権力者との馴れ合いを「取材」と言い張る業界人たち
 5月29日付『朝日新聞』オピニオン欄に掲載されたコラム「池上彰の新聞ななめ読み」(写真/電子版)を読んで、ほんとうにびっくりした。
5月29日付『朝日新聞』オピニオン欄に掲載されたコラム「池上彰の新聞ななめ読み」(写真/電子版)を読んで、ほんとうにびっくりした。
《黒川氏との賭けマージャン/密着と癒着の線引きは》と題したコラムは、『産経新聞』記者2人と『朝日新聞』社員(元記者)が「定年延長問題」真っ只中の東京高検・黒川弘務検事長とコロナ緊急事態宣言中に賭けマージャンをしていた件について、こう書いた。
《黒川検事長という時の人に、ここまで食い込んでいる記者がいることには感服してしまう。自分が現役記者時代、とてもこんな取材はできなかったなあ。朝日の社員は、検察庁の担当を外れても、当時の取材相手と友人関係を保てているということだろう。記者はこうありたいものだ》
あのとんでもない賭けマージャンが取材? こうありたい? 池上氏は本気でこんなことを考えているのか、それとも、大手紙記者たちのあきれ果てた行動に対する皮肉、褒め殺しなのか。だが、後に続く文章を読むと、どうやら「本気」のようだった。
池上氏はさすがに、《いくらなんでも賭けマージャンはまずいだろう》としつつも、自身のNHK社会部記者時代の経験に触れ、《たいした特ダネも書けないまま警視庁担当を外れ》た《自分のふがいなさに情けなくなります》と書いていた。
つまり、警察に食い込めず、特ダネを書けなかった自分と比べ、高検検事長と賭けマージャンを繰り返していた記者たちを《ここまで食い込んでいる》と評価しているのだ。

『朝日』の読者は、こんな池上コラムを読まされて、賭けマージャン問題に対する『朝日』のホンネを「そうだったのか」と教えられたことだろう。
もう一つ、「冗談じゃない」と思った記事・コメントがあった。5月22日付『東京新聞』「こちら特報部」欄に掲載された元『読売新聞』記者・大谷昭宏氏の談話だ。
《「私も刑事とよく酒を飲んだりマージャンしたりした。地方の検事ともよく遊んだ。記者の多くは『いっぱいのコーヒーより一献の酒』を飲める関係を目指した」》
そうして《大谷氏は殺人事件でスクープを記事にし、刑事の飲酒運転など不祥事もすっぱ抜いた》と記事は書いている。
「スクープ」というが、親しい刑事から情報をもらい、他社よりほんの数時間早く「犯人」情報を報じることに、いったいどんな社会的意味があるのか。そんな警察情報鵜呑みの報道で冤罪作りに加担し、人権侵害を繰り返してきたのが、日本の「事件報道」だ。
大谷氏は、「相手組織の批判記事」に関しても述べている。
《「取材先を大事にするほど批判記事は書きづらくなる。それでも書き、『あいつなら仕方がない』と思わせる関係をつくれるかに尽きる。今回の賭けマージャンで、記者たちは黒川氏に厳しいことを書けるのか。互いに悪い意味でズブズブの関係になってしまったようだ」》
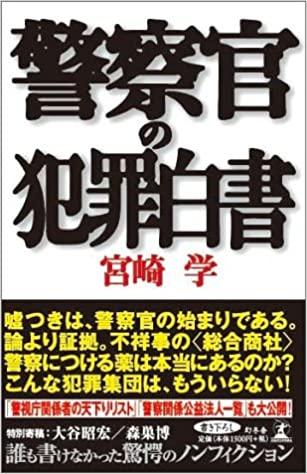
――ある時、大阪府警刑事部長に「東大出のとんでもない」キャリアが赴任した。毎夜、キタの新地で遊び回り、そのツケを全部、捜査費に回す。そればかりか、知恵もないくせに捜査に口出しし、自分の知らない事件情報が報道されると金切り声を上げて騒ぐ。そこで一課担当記者たちが相談し、各社が持っている不祥事を出し合うことになった。
《七社ほどがひそかにつかんでいて記事にしていない警察、とりわけ刑事部関係の不祥事を出し合うと、あるわあるわ、あっという間に数十件になった。とりわけS社のS記者が一人でつかんでいた不祥事だけでも十件以上ある。これでサツに揺さぶりをかけていたんだから、S社から特ダネが出るはずだ》
記者たちはそれをまとめて刑事部長のところに乗り込み、「一週間に一本ずつ記事にしてやろうか」と脅した。このキャリアは、以後大阪を去るまで青くなって震えていた――。
大谷氏はその中で、《不祥事をいわば取引材料にして警察サイドとの交渉を怠らず、一定の緊張関係を保つことは私たちサツ回り記者にとっては常識であった。だからこそ、その交渉の末に、当事者の内々な処分や組織の改善を求めることも、より大きなスクープを聞き出してすっぱ抜くこともできたのである。そこには警察とマスコミの、私にいわせていただければほどよい力関係が働いていた》と書いていた。
警察の不祥事に関して記者たちがつかんだ情報は記事にしない。それは、捜査情報をリークしてもらうための「取引材料」に過ぎなかった。
警察・検察の裏金作りなど間違っても記事にはしない。日本の大手メディアと警察・検察の間柄は、まさに「悪い意味でズブズブの関係」=馴れ合いそのものだった。
それでも、これを「取材活動」と言い張るのが業界人だ。彼らの主張を大きく取り上げる新聞は、警察・検察との「ズブズブの関係」を改める気はないようだ。(了)
Created by staff01. Last modified on 2020-05-30 22:01:26 Copyright: Default
