太田昌国講演録「ヒューマニズムとテロル」〜大道寺将司さんを追悼する
2017年8月11日・東京琉球館
2017年5月24日、確定死刑囚の大道寺将司さんが、収容先の東京拘置所で多発性骨髄腫のため亡くなった。68歳だった。大道寺さんは、1970年代「連続企業爆破事件」を起こした「東アジア反日武装戦線」の一員だった。1974年8月の三菱重工業ビルの爆破では、8人の死者と300人以上の負傷者が出た。後日、大道寺さんらは、自らの過ちを認めている。8月11日、東京・駒込の東京琉球館で、彼を追悼する催しが行われ、評論家の太田昌国さんが「ヒューマニズムとテロル」と題して講演を行った(写真)。1階の小さいな会場に40人以上の人たちが集まり、外の歩道まで溢れる盛況だった。この問題への関心の高さを窺わせた。最初に、2012年に放映されたNHKのETV特集「失われた言葉をさがして 辺見庸 ある死刑囚との対話」が上映され、その後、太田さんが約1時間にわたって講演を行った。それは、「東アジア反日武装戦線」問題にとどまらず世界の革命史を俯瞰した根源的問題提起となっている。以下、紹介する。(レイバーネット編集部)
1、問題の核心

日本の監獄制度が厳しいことは皆さんご存知だと思います。世界各国の水準とくらべても、きわめて厳格で厳しい。仮に罪を犯した人であっても、その人たちが、将来的に社会復帰できる条件を十分満たすような形で、行刑制度が行われていないということはよく知られていることです。とりわけ死刑囚にとっては、死刑が確定した途端、それはいつか死刑が執行されるべきものとしてしか、拘置所は扱いませんから、そのような存在として、処遇されるわけです。
大道寺君の死刑が確定したのは、1987年で、ちょうど30年経っていたわけですが、その間には、処遇という意味ではいくつかの変遷がありました。面会できる人、文通できる人、差し入れできる人、それらの件で、いくつかの変化がありました。最終的に面会・文通できた知人・友人は、僕をいれて6人でした。辺見庸さんは除いています、別枠なので。その6人の中では、再審を担当している弁護人を含めたメーリング・リストを作っていて、それぞれが面会した結果を、報告しあう。伝達すべきこと、獄中の将司君の状態などを報告しあっていました。僕は原則最低月1回は面会するようにしていたのですが、他の5人の人たちもそれぞれ自分たちの事情に応じて、月1回だったり、数か月に1回だったり、少なくとも昨年の夏ぐらいまでは面会できていたので、そういう意味での情報の交通形態はあったのです。
たとえば、大道寺君と法政大学時代の友人だった仮にN君としますが、彼と大道寺君が面会すると、1回15分か20分の面会ですが、いろいろな話題の中に、お互い年を取ったので、健康状態の話が出てくる。そうすると、大道寺君は2010年から多発性骨髄腫を患っていますから、どうしても癌の話、病気の話になる。Nさんも別の種類だけれども癌を患っている。お互いが病気の話で盛り上がって、それでだんだんと「そういえば、太田昌国というひとは、まったく病気をしない。風邪ひとつひかないそうだ。ほんとにあれで人の痛みがわかるのだろうか、身体の痛みがわからない奴に人の痛みがわかるのだろうか」という話になって、「昌国さんは、きっと人の痛みはわからない奴だ」と言って、二人で盛り上がったという面会報告がメーリング・リストに流れるのです。ですから、大道寺君と面会している6人の間では、僕は体の痛みをまったく知らず、何十年も風邪ひとつひかないで過ごしてきて、したがって人の痛みを知らない奴だと、そういう見方が定着しているわけです。事実、わたしはそうなのです。風邪で寝込んだことすら、もう何十年とありません。風邪かなと思ったら、熱い卵酒を飲んで寝ると、翌朝にはけろりとしているのです。そういう意味で人の痛みがわからないわたしが、これからしばらくお話します。

つまり、目的は手段を浄化するのか、という問題です。これは人類が何事か、目的意識をもって行動した人たちが、何らかのそれとは逆の結果をもたらした、その問題をどう解釈するかをめぐって、ずっと古今東西、あり続けてきた問題です。目的は手段を浄化するか。正しい目的があったから、どんな手段をとってもそれはよかったのだと考えることができるか。そういう問題として現れると思います。1974年8月30日、大道寺君が属していた東アジア反日武装戦線狼部隊が三菱重工ビル前の街路に設置した爆弾の爆発によって、8人の死者と385人の重軽傷者が出ました。それから3週間ほど経った9月23日付けの彼らの声明では、「日帝中枢部にいる」――日本帝国主義の中枢部、丸の内界隈というのは、三菱重工ビルがあることも含めて、いわば日本のトップクラスの経済機構の中心的企業が集中している地域である。そのことを指して「日帝中枢部」と彼らは表現したわけですが――それは、そのような所にいた人間であるから、それは植民地人民に寄生している日帝本国人である、という規定を行って、8月30日の闘争は正しかった、そういう声明文を発表したわけです。
もちろん大急ぎで言っておかなければならないわけですが、三菱重工ビル前爆破自体を、彼らは自分たちの意図とは反した結果をもたらしたとして、その日の夕方、結果を見て、考えたわけです。9月23日の声明に関しても、いかに決定的なひどい過ちであったかということを後日ふりかえるわけです。けれども、とりあえずその段階では、そのように声明をしてしまった。だが、「本心」は別なところにあった。解放闘争とか、革命運動とか、抵抗闘争とか、そういう文脈の中で或る行動を選択した主体自身が、その行為がもたらした結果に驚き、悔やんでいる。その意味では、今までの人類の中の革命戦争、解放闘争、抵抗闘争というものの中で、そこで生じた死者の問題が、どうとらえられてきたのか、という問題としてわたしたちの前には差し出されるだろうと思います。普遍的な問題になるのです。
これは広く言えば政治の世界の話ですから、よく言われるように政治の世界の中では、その中で狭く考えてしまったら、「奴は敵である、敵を殺せ」という論理が貫徹してしまうというのが、古くから人間の歴史をいろどってきた、一つの考え方である。もし、それでいいという風に、そのような考え方に安住してしまうのであれば、それは、もちろん解放もなければ、抵抗もない、革命もない。いわば人を殺すということに意味を見出してしまうような、そのようなレベルに行ってしまうわけで、そうではない考え方をどこかでわたしたちは見出さなければならない。あるいは、過去の人間の歴史の中に、そのような過ちを見つけた上で、それを克服しながら、確信をもって前に進まなければならない。そういうことになると思います。
たとえば、帝政ロシアの時代にはナロードニキという一群の人たちがいました。もうすでにマルクス主義が一定の影響力をもって、世界のある一定の人びとに影響力を及ぼしていた時代ですが、ロシアの場合には、それとは別な人民主義者と訳されますが、「ブ・ナロード(人民の中へ)」というスローガンの下で、帝政ロシアの圧政の軛から、どのようにロシアの民を救うか――基本的には、インテリゲンツィアの運動でしたから、そういう取り組みになる。彼らはあまりにも帝政の軛が巨大であるので、もう象徴的な最高責任者を個人テロでやるしかないというような形での皇帝暗殺の試みが何度もなされたわけです。セルゲイ大公をねらったカリヤーエフという人も爆弾を持って、その大公の馬車が通る時間を推し量って待ち伏せする。しかし実際に来たセルゲイのそばには、幼い子が坐っていた。それはセルゲイの甥と姪なのですが、それを見てカリヤーエフは、爆弾を投げつけるのをやめてしまう。組織に戻ると、なぜ組織決定を覆したのだと、批判する人もいれば、カリヤーエフの「子どもたちがいたから」ということばを聞いて納得するメンバーもいた。そういう問答が続くというのが、サヴィンコフという人が書いた本の中に出てくるわけです。付け加えておけば、カリヤーエフは後日再度セルゲイ大公暗殺を試みてそれに成功し、最後には死刑になってしまいます。
*レービンによって描かれたナロードニキ逮捕の瞬間/モスクワ・トレチャコフ美術館蔵
それに題材をとって、フランスの作家のカミュは、『正義の人びと』という戯曲を書くわけです。そうするとここでは、カリヤーエフたちが考えた政治的目的からすれば、ツァーリの体制を支える最高責任者の一人としてのセルゲイを殺すことは絶対的な正義、しかし、実際、現場に行ってみたら、そこには、罪を問うには幼すぎる二人の幼子がいた。巻き添えにすることはできないという選択をしたカリヤーエフの在り方をどう考えるか。そういう問題として出てくるわけです。
さらに、いまの若い人は知ることもないと思いますが、ソ連時代の作家にミハイル・ショーロホフという作家がいました。僕の世代、1960年代、高校・大学になっていた世代にとっては、まだまだソビエト共産主義に対する幻想があったり、どこか希望の証ではないかと思うところもあったりしたから、豊かな文学作品が生み出された19世紀ロシア文学の延長上でソビエト革命以降のさまざまな文学は読むわけです。ショーロホフに『静かなるドン』という長編小説がある。それはソビエト革命が成って以降の、正規軍となった赤軍とそれに対抗する反革命軍との闘いが描かれた作品である。
その中の描写にたとえば、赤軍兵士たちの間で、自分が直面した、自分が殺してしまった相手は「勤労者だった……その男の手にさわると、それがまるで靴の底みたいなんだ……固くてね……まめがいっぱい出来てた……真っ黒い掌、ひびだらけなんだ……掌じゅう擦り傷だらけでな」と表現できるような人間だった。そうすると、同じ勤労者を〈敵〉として殺してしまったことへの胸の痛みを訴える者に対して、ゴリゴリの共産党員の兵士が出てきて、「どうやってみたところで、叩き直せやしない」と答える。ある人物を殺したことを、こういう論理で正当化する、そういう会話が出てくる。このような、否応なく戦争に追い込まれた人間たち、悲劇的にも追い込まれた人間たちが、このような出会い方とそこでわき起こる感情をどう考えるか。埴谷雄高風に言えば、革命の目的は「制度」の変革であるのに、或る時代の「制度」の中で特定の役割を演じている/演じさせられている「個人」を殺すことを自己目的化してしまったら、その先にどんな展望があるのか、ということです。
次の件については、僕はここでも何回か触れたことがありますが、シモーヌ・ヴェイユというひとにも言及します。彼女は、スペイン内戦の過程で、この問題に直面したのです。シモーヌ・ヴェイユはもちろん、フランコのファシスト軍に対して闘うスペイン共和国派の勝利を願い、そのために内戦下のスペインに行って活動しようとした。その気持ちはまったく変わることはないけれど、しかし、その戦争の過程の中で、共和国派に参加している貧しい農民や労働者の軍隊が、いわば敵軍の兵士に対して、きわめて残酷な仕打ちをする現場を見てしまった。あるいは、そういう報告を見聞き、読んでしまった。そうすると、戦争という、人びとを否応なくまきこんでしまう過程の中で、なぜ普段はあれだけまっとうな市民として、庶民としてふるまうことができる人たちが、〈敵〉に対する残虐な行為をあえてやってしまうまでの人間と化してしまうのか、ということを考えて、彼女は一層、戦争に対して、あるいは革命という問題に対しての考察を深めることになる。そういう問題としても出てくる。

僕は、当時見たときも、いま見直してみても、1950年代後半のアルジェリアの状況を考えた場合に、あの爆弾闘争を間違っている、暴力を使ったから間違っていると、断定する勇気は出てこない。当時も出てこなかったし、今もそうは言えないような気がする。それはつまり、アルジェリアにおける、フランスによる植民地支配というものが、日々のアルジェリアの民衆を抑圧するものとして、きわめて具体化している日常がある。一体そこにフランス軍という強大な軍隊が入って、その暴力装置によって植民地支配が貫徹されている時にも、人びとに残されている抵抗の手段は、あくまでも平和的な手段しかないだろうと遠くから主張することは僕にはできない。当時も思ったし、今もあらためて思う。これが正しいかどうかわからない、僕自身。これは、あとで、今日に限らず今後の討論の機会になっていいと思うのですが。
それは、たとえばアルジェリア革命の場合は、フランツ・ファノンというカリブ海のフランス植民地であったマルチニック出身の精神科医がいます。彼はパリに留学して、精神医学を学ぶわけですが、それはちょうどアルジェリアの解放闘争が高揚する時代であった。それで彼は、アルジェリアの解放闘争にスポークスパーソンとして身を投じるわけです。ですから解放戦線の機関紙や、闘争の背景にある理論的なことがらについての仕事に携わる。その中で一番有名な著作が『地に呪われた者』ですが、その本は植民地社会がいかに植民者と被植民者を見るからにわけへだてた社会であるかということを、きわめて論理的に、観察的に分析するわけです。そんな著作も合わせて読むと、当時アルジェリアの解放戦線が取った、暴力的な手段も含めた、爆弾闘争を含めた闘争が、こんな遠くから否定できるものでもないだろうという考え方が、なかなか僕はぬけきらない。そういう感じがするわけです。
2、三菱の「背理」を生み出した根拠
 翻って、先ほどからふれた、74年8月30日の狼の三菱をどう考えるか。それは、やっぱり僕は、当時もそうだったし、今もこれはやってはいけない闘争であったと、きわめて否定的なんです。なぜか、それはやはり、その社会における人々を支配し抑圧する構造の具体性の問題だと思う。そしてそれに対する抵抗の闘争がどうあるべきか、という問題にかかわってくると思う。アルジェリアの場合は、フランスによる植民地支配は日々の人びとの生活を支配する、まさに日々抑圧している具体的な実態を持っていた。抑圧構造自体が目に見える具体性があった。そういう時に、様々な合法的な集会やデモや抗議活動が考慮されない、一顧だにされないそのような条件の中で、人びとはおそらくやむを得ずあのような形の抵抗闘争に訴えざるを得なかった。そういうことがあったと思う。
翻って、先ほどからふれた、74年8月30日の狼の三菱をどう考えるか。それは、やっぱり僕は、当時もそうだったし、今もこれはやってはいけない闘争であったと、きわめて否定的なんです。なぜか、それはやはり、その社会における人々を支配し抑圧する構造の具体性の問題だと思う。そしてそれに対する抵抗の闘争がどうあるべきか、という問題にかかわってくると思う。アルジェリアの場合は、フランスによる植民地支配は日々の人びとの生活を支配する、まさに日々抑圧している具体的な実態を持っていた。抑圧構造自体が目に見える具体性があった。そういう時に、様々な合法的な集会やデモや抗議活動が考慮されない、一顧だにされないそのような条件の中で、人びとはおそらくやむを得ずあのような形の抵抗闘争に訴えざるを得なかった。そういうことがあったと思う。
翻って、74年8月の日本は、もう60年代の高度経済成長を経たあとの産業社会です。産業社会というのは、社会の構造というもののが、非常にソフィストケイトされた、洗練されたものになるわけです。抑圧もむき出しではない。人びとが、抑圧の構造、支配の構造を、そうリアルに感じとることはできない。騙されてしまいがちな、それぐらいソフトな洗練された方法で、産業社会における支配・抑圧は行われているわけで、それに対して、爆弾を使った武装闘争、象徴的な建物に対する攻撃をやることが、そのような支配・抑圧の構造を暴露し、克服していく上ではたして有効なのか。そういうところで議論されなければならないと思う。爆弾は、仕掛ける人間を安全な場所におくことのできる、非対称的な、絶対的な「武器」でもあります。
三菱の時も、2001年の9・11のワールドトレードセンターとペンタゴンの時も、あゝいう時に僕は、自分がその場にいて自分が殺されて許せるか、許せないかという形でよく考えるんです。僕は、丸の内なんてほとんど行ったことのない人間であるけれど、仮にあの時、丸の内にいたとする。存在形態にもよりますよね。どういう仮定をするかによるのだけれど、しかし、とりあえず一般的に丸の内に僕がいて、三菱の社員でいてもいいんですよ。そして、爆弾で殺される対象となっても、止むを得なかったと、自分を納得させるかというと、それはできない。自分があそこで犠牲者であることが納得できない以上、これは間違っていたと思います。9・11の場合は、ペンタゴンにいたらしようがないと思うかもしれないけれど、ワールドトレードセンターにいたら、僕はちょっと納得できないなと思いながら、一体この人たちは、何でこんなことやったんだろうと反問せざるをえなかった。
その場に自分がいたと置き換えてみるようなことは、これは仮定ですから、リアリズムでもなんでもないのだけれど、しかし、そうすることによって、人はもう少しそこで起こった出来事をよりリアルに感じながら物事を考えることができるのではないかと思います。だからブリュッセルにいたら、ニースにいたら、パリにいたらと、いろんなことを、ここ2、3年の状況の中では考えるわけです。やはりちょっとこういう死に方はたまらんなあと思うことが、最近のいわゆるテロリズムの中の死に一貫して感じることが多いです。メディアや各国政府のように、2001年に米国が発動して、16年後の現在にまで続く「反テロ戦争」による死者――つまり、戦争という「国家テロ」による死者は軽視しておいて、小集団の「テロリズム」のみを非難する立場には、いかなる場合にも立たないけれど、それにしてもわが身をそこに置いてみたらこんな死に方はたまらんと、もう少し僕にもやることがあるから生きさせてくれ、いうところで問題を考えていきたい。それが、現実に生まれてしまった犠牲者にも繋がる道だと思う。
政治の中の死というものは、憎しみと報復の連鎖の中で自己回転してしまうので、どこでどう断ち切るかという強い意志を示さないといけない。積極的に持たなければならない。そういう問題だと思う。ですから、そこで踏みとどまる場所をどういうふうに我々自身が見つけるか。現代史の教訓としては、例えば1979年の中米ニカラグアの革命の後に、死刑制度が即刻廃止された例があります。ニカラグアの独裁政権も一族支配で、1930年代から続くソモサという政権でした。そこでは政権の中枢部の人間や、軍隊や警察に巣食う幹部の連中は、とんでもないことをやった。長年かかって、独裁体制を打倒する革命が成就した。その時、解放運動の指導者の一人が拷問した元の軍人や警官を前に、革命が勝利した後ですよ、「自分の復讐は君たちを死刑にもしない、虐待もしないということだ」と言って、死刑制度を廃止するわけです。最高刑懲役30年、軽い罪の人は塀のない、開放刑務所に入れるという施策を革命直後にやるわけです。

二番目、何度も触れますが、三菱の背理を生み出した根拠は何だったのかを考えなければならない。冒頭で言いましたように、「彼らの意図は、純粋であった。その純粋な意図を忘れてはいけない」というところで、僕らがとどまっていることは、おそらく違うだろう。なぜ、あのような間違いが起こったのかといことを同時に考えなければならない。彼らが出した機関紙の「腹腹時計」の理論編というのを、皆さんがどこまでお読みになっているかちょっとわかりませんが、彼らがこの中で主張した考え方というのは、彼らが批判してきた伝統的なマルクス主義の考え方からすれば、階級闘争論ですから、一国内の支配階級とそれに抑圧されているプロレタリア階級の闘争として、一国内の階級闘争として基本的にとらえる。彼らがこの段階で出した考え方は、そうではなくて、日本のような高度産業社会が出来上がっていく上においては、近代以降の歴史の中で植民地化したり侵略した被抑圧諸国、被抑圧民族との関係の中で考えなくてはならない。つまり民族・植民地問題を重要な契機として導入して、その中で現在の日本の在り方を考えなければならない。
日本はアジアで唯一の植民地主義と侵略戦争を実践した国になってしまったわけですが、それはもちろん明治維新によって、近代国家が成立して以降の歴史です。その歴史を考えた場合に、日本の植民地主義というものがいかに実践されたか、それを背景としたアジア諸国に対する、および広く後半の段階では、アジア・太平洋諸国に対する侵略と軍政支配というものが、どのようなきっかけで成立したか、そういうことを考えた上で、敗戦によってまったく新しい国に生まれ変わったといわれる戦後日本の中で、しかし、戦争と植民地支配によって富を蓄積した企業が一つも変わっていないではないか。戦争を支え、植民地支配を支えた企業が、官僚たちが、自民党に連なる政治家たちが、それらが全部、様々な策を弄して生き残った上に、戦後日本の平和主義があった。そういう問題提起であった。
それを1974年、敗戦から30年の段階で提起するというのは、かなりたいへんな理論的というか、歴史解釈的努力が必要だったと思います。そういう意味では非常に鋭い問題提起であったということは言っておかなければならないと思います。ただこの当時の『腹腹時計』を読みかえしてみると、そのある種理論的な突出しの鋭さというのは、いわば枝葉末節を切り捨てることによって成立していた。もう少し複雑な歴史過程として、あるいは現状分析として、本来ならば考える枠組みの中に入れなければならないことを、切り捨てることによって出た理論的な鋭さであったというふうに考えることできると思います。たとえば、〈反日〉ということば。しかしその〈反日〉を唱えたのは、日本人である。日本人が〈反日〉という時に、一体どういう水準で問題提起をすることになったのか。〈反日〉という立場に自分を置いて、その問題意識を持たない圧倒的多数の、99%、100%に近い日本人に問題提起をするときに、一体その〈反日〉という問題提起を行い得る主体はどのように可能なのか。〈反日〉を言う自分たちは何なのか。
この中には、〈反日意識〉がないことによって、しようがない改良闘争ばかりやっている日本の労働運動、革命運動の中にあって、唯一革命的な存在は、山谷や釜ヶ崎にいる流動的下層労働者である、という規定がなされていく。その延長上で世界の現状の中で、唯一革命的なのは、被植民地人民である、そういう規定がなされていく。これは、ある一つの階層や民族を固定的に絶対化している、そういう考え方になる。我々は自分たちが生きていく人生の中で、人間は状況の中で自分も変わる、あるいは担っている運動も変わる、存在そのものが変わっていく、ある種可変的な存在であることを知っている。だからある固定的な階級や民族が、それ自体が革命的であるとか、反革命的であるとか、ある民族が革命的であるとか、反革命的であるとか、というふうにとらえることはきわめて観念的であるということを日常的な実感の中では、知っているわけです。しかし、彼らはあえてそこを特定の階層が、日本であれば日雇い労働に従事している山谷や釜ヶ崎の下層労働者だけが革命的主体であると規定した。世界の中では被植民地人民だけがそうであると規定した。そういう時にいったいどういう、行動方針が出てくるのかという問題がある。
そのような状況の中での、運動や人間の可変性を想定していない考え方、被植民地人民の中からだって、とんでもない奴はいるし下層労働者の中にもどうしようもない人間もいるし、というのが我々が日々暮らしている中でもつリアリティー、実感であって、これに観念的な理想社会を作ってしまっては、現実からかけ離れていくといえる。その問題とからんでくるのではないかと思います。ですから大道寺君が獄中で、松下竜一さんの『豆腐屋の四季』を読んで感動して手紙を書いたというのは有名なエピソードです。それがやがて松下竜一さんが大道寺君に面会を重ね母親の幸子さんにインタビューして、『狼煙を見よ』という作品に仕上がっていく、というのもご存知の方が多いと思います。これはやはり、大道寺君自身も書いていますが、自分たちが闘争していた時に考えていた人民とか、民衆とかそうしたものが極めて観念的なものであって、たとえば北九州の片田舎の中津で、進学しないで家業である豆腐屋を継いでシコシコと働いていた松下さんが、日々その生活の中から生み出した文章に、あゝ自分はこういう世界を知らなかった、あるいはこういう世界と切れたところで民衆というものを考えていたと、そういうところにゆくわけです。ですからそのような問題として、考えなければならないだろうと思います。
3、テロルの過ちを越え得るヒューマニズムはあるか
それから、1970年代の日本において、爆弾という武器を使用する根底にあった価値観をどう考えるかという問題もあると思います。21世紀に入って以降、私たちは、「反テロ戦争」を呼号する米国が、自国の兵士が決して傷つくことのない無人機爆撃やドローンによる攻撃を行なって、中東地域の民間人に多大の死傷者が出ている事実を知っています。これに抗議する側が行なっている、いわゆる「自爆テロ」も、きわめて悲劇的です。自らが設置した爆弾の破壊力を知った東アジア反日武装戦線〈狼〉のメンバ−が、その結果に驚愕し、茫然自失となり、自らが担った行為に絶望感を抱いた事実を忘れるべきではないと思います。このように考えた上で、テロリズムの過ちを超えうるヒューマニズムはあるのかというところに来ると思います。ヒューマニズムとテロルという問題設定をした以上、そのようなところで最後は考えないとならないと思う。

ところが、先ほど言った俳句の世界は、どこかでフィットしたのでしょうか、彼自身が俳句を作り始めるということになっていくわけです。公表するまでにはほとんど万の句を捨てたと言っていたと思いますが、仮に一日10句作ると年に3650句できるわけだから、3年間ぐらいの「下積み」の時期があったとして3年間で1万くらいになるわけで、それを超えてやっと納得できる句ができ始めた。それ以降は、最終的に4冊の句集を出したわけですから、彼にとってはまたとない自己表現の場所であったと客観的にも思います。
その俳句の中でさまざまな世界を詠うことになるわけですが、僕が読んでいて圧倒的に印象が深いのは悔恨の句です。三菱で死傷させてしまった人びとと自分の関係を詠む句である。ですから彼にとっては、テロの過ちを乗り越えることができるヒューマニズムがあり得るかということに対してはまったく絶望していた。そんなことは出来っこない。〈死〉は絶対的なものであり、自分の行為によって他者に強いてしまった〈死〉は、取り返しのつかないものなのだから、それはどんな意味でも乗り越えることはできないという、そういう壁に塞がれての、42年間だったのだろうと思います。
それは去年の秋だったのですが、彼が意識がある中での最終回の面会になったと思います。面会室に入った僕にいきなり、一言二言かわした後だったと思いますが、「人を殺めたことのある人間と、殺めたことのない人間との間には絶対的な壁がある」と言った。〈壁〉というのは、おそらくわかりえない、わかりえないというのは、殺めたことのない人間には殺めたことのある人間の世界が、どんな精神的な境地なのかをわからないだろうと、そういう意味だとその時も思ったし、その後もそのように反芻するわけですが、そういう風に彼は言ったことがあった。それは今思えば、彼はほとんど死を覚悟していた、もうこれが回復することはないのだろうと思って、いろいろな書く文章でも面会時のことばでも今までは言わなかったことを結構言っていたんです。そういう言葉の一つだったと思います。その言葉もまた、自分が行ってしまった74年8月30日の行為が彼にどれほどまでに彼の心に重くのしかかっていたかを示している。そういうことだったと思います。
本人はそう思ったとしても本人ではない僕らは、もう少し客観的な場所から冷静に物事を見ていいと思うのですが、彼が俳句の世界の中で築いてきた一つの表現の中に、自分の行動を顧みて死者との関係性を詠んでいるあれらの句が一つの作品として、文学作品とあえて言わなくていいですが、一つの表現としてどれほどの高みに至っているかを考えたのです。人が「罪と罰」とか、「悔悟と許し」とか「罪と新生」とかを考える上で、非常に示唆するところが多い作品になっているだろうと思います。
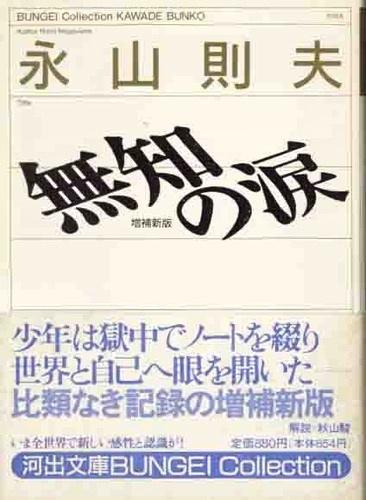
簡単に言えば、その年、ペルー大使公邸人質占拠事件が起こっていて、日本の報道はほとんど、人質安否報道に純化したわけですが、唯一、一度朝日新聞に、このような事件が起こるペルー社会の背景として、路上で働く子どもたちの記事が載ったことがあった。その子どもたちは、パン屋をやったり、花屋をやったり、レンガ屋をやったり、助け合いながら相互扶助的な組織を作って活動しているという記事が出ていた。これはわたしたちの想像ですが、永山氏は自分の子ども時代と異なって、そのようにペルーの子どもたちが、貧しい厳しい境遇の中で、互いに助け合って、自立する、家族を助ける、自分たちが自立する、そういう根拠を見出していることに、一つの希望を持った。だから、たくさん売れている自分の本の印税は、その子たちのために使ってほしいという遺言になったのだろうと解釈したわけです。奨学金として毎年、平均50万円がペルーの子どもたちに送られている、そういう活動です。
ですから、仮に冤罪の場合はとんでもない話ですが、実際に罪を犯している、人を殺めて死刑囚となってしまった、実際に日本の現在の死刑制度存続状態の中で、処刑されてしまったそのような人も、いま言ったような形で、生き変ると言いますか、別な価値観を持って、人びととの交わりの中で、別の人生を歩むことができると、そういう現象がたくさんあるわけです。ですから、人を殺めたこと自体が、死をもって償わなくてはならない、死をもって購わなくてはならないという固定的な観念でとらえるべきではないということがどうしても残ると思います。
先ほど、彼らが理論的な提起の問題として、民族・植民地問題に注目し、これを大きく取り上げたという、それは日本の現状を見れば、改めてその先駆性がわかるだろうと思います。現在日本に成立して長期政権になっている政権の在り方を見ても、あの人物が2006年に第一次内閣を組織した翌年、2007年に公然と登場したのが、在特会であったという関係性から見ても、日本の戦後史はとうとう民族・植民地問題を具体的に解決することがないまま、昔の姿かたちを保ったまま70数年後の現在、この社会に復活しているのです。あの時の戦争を推進した勢力、それを支えた自民党的なメンタリティーを持った政治家たち、それを支えた官僚機構、それらがすべて生き残った上で、現在の日本の姿があるんだという因果関係の中でとらえた時に、彼らが提起した問題は、とうとう十分にこの社会の中で理解され、その問題があるとすれば、その問題点を克服するような運動として大きく広がることもないまま現状に来ているという、きわめて残念なことですが、その姿が見えてくるというふうに思います。
彼らが非常に関心を持った日本と朝鮮の関係があります。その朝鮮はいまだに、日本帝国主義の支配の一つの直接的な結果として、南北に分断され、今にいたるまでの、きわめて不幸な状態が続いているわけです。ここ数日間は、朝鮮の若い独裁者と米国のどうしようもない大統領の間で、どんどん事がエスカレートして、このまま、あいつらは本気で、それをやってしまったら、どうなるかわからないというような、危機的な事態にもなっているわけです。この問題はこれとして考えなければならないことですが。韓国からいま出ている歴史的な問題提起は、非常に注目されるものだと思います。権赫泰という人が書いた『平和なき「平和主義」』(法政大学出版局、2016年)、同じ権赫泰さんと車承棋さんが一緒に書いた『〈戦後〉の誕生』(新泉社2017年)――これには中野敏男さんも一緒に書いています――が、それです。
この中で、現代韓国の研究者たちから提起されている問題は、戦後日本は平和憲法の下で「平和主義」を貫いてきたと言ってきている、しかし、実態はどうだったのか、ということの問題提起です。そろそろ時間がないのでやめますが、たとえば僕らも学生時代、一生懸命読んだ、リベラルな思想家として著名な丸山眞男という政治学者がいました。もちろん読むに値する学者だと思っていますし、随分教わったところも多いけれど、たとえば韓国の人から見れば、あれだけ日本軍国主義の問題について考え発言した丸山は、なぜ植民地主義に対する問題意識を欠いていたのか、そういう問題提起をするわけですね。これは、もちろん日本の中でも、丸山さんが死んだ1996年段階で、いくつか指摘のあった論点の一つでした。僕も当時、短いものですが、そのような観点から書いた記憶があります。 しかし、そのような観点で、戦後史をとらえ返す、あるいは、丸山さんのような高名な研究者をそのような視点からとらえ返す方法は、なかなかこの社会では浸透しない。それが、民族・植民地問題だった。これだけ大きな問題を日本国内において、アジア諸国との関係において生み出しながら、とうとうこの問題を自覚化しえなかった、主体化できなかったこの社会の問題としてつながってくるだろうと思うわけです。ですから、いま、韓国については、文学の紹介も随分進んでいるし、こういう思想的・歴史的な問題提起という意味ではいろいろお互いに討論できる、そういう時代が来ているとつくづく思いますから、そうい意味で大事にしていきたい。
これは要するに大道寺君たちが、東アジア反日武装戦線が提起した問題ともつながってくる。彼らは内部から提起したけれども、ようやく外部からもそのような問題提起がなされてきた。この接点でこの問題を、わたしたちの社会が、まともに向き合ってきていない。したがって、きちっと解きえていない。そのために、東アジアとの関係が、これほどぐしゃぐしゃになっている。その現状を考えなおす意味でも、大きな意味を持つだろうと思います。約1時間たちました。いつもはこの2倍話すのですが、これをやると10時半になってしまうので、今日はこれでやめます。どうもお疲れさまでした。
Created by staff01. Last modified on 2017-11-07 09:00:36 Copyright: Default


