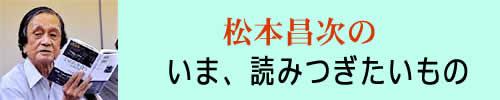第2回 2015年11月1日 松本昌次(編集者)
花田清輝「大きさは測るべからず」
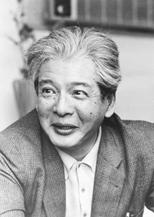 表題は、花田さんが、秋元松代さんの戯曲『常陸坊海尊』に送った言葉です。もともとは、柳田国男の『遠野物語』の一節ーー「白望(しろみ)の山に行きて泊れば、深夜にあたりの薄明るくなることあり。秋の頃、キノコを採りに行き山中に宿する者、よくこの事に逢う。また谷のあなたにて大木を伐り倒す音、歌の声など聞ゆることあり。この山の大きさは測るべからず。」ーーからとられたもので、わずか2ページほどの短いエッセイですが、どんなに花田さんがこの作品の「大きさ」に心打たれたかが、惻々として読むものに伝わってきます。と同時に、わたしには、この「小さな」エッセイに凝縮した花田さんの「大きさ」を感じないではおれません。
表題は、花田さんが、秋元松代さんの戯曲『常陸坊海尊』に送った言葉です。もともとは、柳田国男の『遠野物語』の一節ーー「白望(しろみ)の山に行きて泊れば、深夜にあたりの薄明るくなることあり。秋の頃、キノコを採りに行き山中に宿する者、よくこの事に逢う。また谷のあなたにて大木を伐り倒す音、歌の声など聞ゆることあり。この山の大きさは測るべからず。」ーーからとられたもので、わずか2ページほどの短いエッセイですが、どんなに花田さんがこの作品の「大きさ」に心打たれたかが、惻々として読むものに伝わってきます。と同時に、わたしには、この「小さな」エッセイに凝縮した花田さんの「大きさ」を感じないではおれません。
いまここで、『常陸坊海尊』について書く余裕はありませんが、ひとことでしるせば、戦争中、東北地方に疎開していた学童たちが、東京大空襲で家族や身寄りを一挙に失って孤児となり、戦後、それぞれ農家や漁師に貰われて行く苛酷な運命の行く末を、民間説話として語りつがれる常陸坊海尊と重ねあわせた作品です。常陸坊海尊は、義経が最期を遂げた平泉・衣川の合戦の折、命が惜しくて主君を見捨て戦場を逃亡したといわれています。その罪を背負って、以後750年、海尊は罪の深さを懺悔しながらいまなお東北の山村をさまよっているというのです。荒唐無稽と思われそうですが、この作品には、花田さんが言うとおり、「生きることもできず、死ぬこともできなかった、戦争末期のやるせない日本人の魂が……あますところなくえぐり出されてい」るのです。
花田さんは、柳田国男が、『遠野物語』の初版本のトビラに、「外国に在る人々に呈す」という献辞を入れたことにふれて、次のように書いています。ーー「それは、その本のなかにあつめられた東北の伝説によって、人々のノスタルジアをそそるためではなく、それらの伝説をうみだした、底辺に生きるものの悲痛さを、たえず思い出してもらいたかったためにちがいありません。おそらくこの戯曲のトビラにも同じ献辞が必要でありましょう。なぜなら、新劇の関係者たちはーー作者も、演出者も、俳優も、観客もひっくるめて、一言にしていえば、『外国に在る人々』であるからであります。」ーーと。
このエッセイは、わたしも企画・制作者の一人として関係していた劇団演劇座が、1967年9月、『常陸坊海尊』を初演したさい、パンフレットに掲載されたものです。それゆえ、「新劇の関係者たち」への献辞の必要が強調されていますが、果たして、「外国に在る人々」は彼等だけでしょうか。否です。花田さんは、芸術家たちに、思想家たちに、政治家たちに、社会運動家たちに、ひろく知識人たちに、市民たちに、この献辞を、そして『常陸坊海尊』に描かれた現実を直視して欲しいと願ったのだと思います。そしてまた、「底辺に生きるものの悲痛さ」は、なにも、この戯曲に描かれた戦争中や、戦後の一時期に限ったことでないことは、いうまでもありません。
いや、ますます、「外国に在る人々」が増殖しているといっても過言ではないかも知れません。そして「底辺に生きるもの」たちとの隔たりも見えにくくなっていると言えます。そのことのいちいちについてはご想像にまかせますが、「外国」という言葉の意味するものとは何か。戦争中に書いた『復興期の精神』から、最晩年の『日本のルネッサンス人』(1974年)に至る花田さんの仕事は、誤解を恐れずに言えば、この「外国」との格闘だったと言えるかも知れません。
<引用文献>
「大きさは測るべからず」『花田清輝全集』第十三巻(講談社)及び戦後文学エッセイ選1『花田清輝集』(影書房)/柳田国男『遠野物語』(各文庫)/秋元松代『常陸坊海尊・かさぶた式部考』(講談社文芸文庫)
Created by staff01. Last modified on 2015-11-01 14:33:27 Copyright: Default